

 高島さんの書く文章は、商業用文章はもとより日常の手紙なども常に手書きの縦書き、しかも旧かな遣いらしい。徹底していることがすばらしい。 高島さんの書く文章は、商業用文章はもとより日常の手紙なども常に手書きの縦書き、しかも旧かな遣いらしい。徹底していることがすばらしい。
『お言葉ですが…』で、縦書き横書きがテーマの時、故・向田邦子さんが提唱していた「縦の会」のことを引用していた。同じ週刊文春誌上で高島さんの二十年前にエッセイを連載していた向田さんも「縦書きを残そう。名つけて『縦の会』でどうだろう」と提唱していたのだ。その時のことを覚えている。私はあの頃、向田さんの作品をよく読んでいた。週刊文春を毎週のように読むようになったのは『疑惑の銃弾』からだ。これもよく覚えている。
この回の高島さんの文章で、「縦の会」が三島の「楯の会」のもじりであることを注釈していたことが印象深かった。うすらバカのぼくでもそれはリアルタイムで経験したことだからすぐにわかるのだが、若い人にとっては歴史上の出来事なのだろう。よほどそういうことに興味がある人でなければ「楯の会」はもうマニアックな知識なのかもしれない。そのことのほうが強烈で、向田さんの「縦の会」のことはふっとんでしまったものだった。
---------------
 現代小説は一切読まないという高島さんが、何の因果か向田さんの本に関わったらしい。もう発刊されたことは知っているのだがまだ手にしていない。何度か探したが見つからなかった。けっこうマイナーな出版社だったか。なぜそんなことになったかの大体は知っている。高島さんは日本のサヨクが主張するような「戦前は暗黒」というのを受け入れていない。これは私の両親やその他親戚の生き証人もみな同様に口にするし、先日読んだ随筆では団鬼六さんが昭和初期の活気ある時代について書かれていた。 現代小説は一切読まないという高島さんが、何の因果か向田さんの本に関わったらしい。もう発刊されたことは知っているのだがまだ手にしていない。何度か探したが見つからなかった。けっこうマイナーな出版社だったか。なぜそんなことになったかの大体は知っている。高島さんは日本のサヨクが主張するような「戦前は暗黒」というのを受け入れていない。これは私の両親やその他親戚の生き証人もみな同様に口にするし、先日読んだ随筆では団鬼六さんが昭和初期の活気ある時代について書かれていた。
やたら戦前はすべてが最悪の地獄の時代のように主張する朝日的サヨクにうんざりしていた高島さんは、昭和のよき時代のことを絶妙のタッチで書かれる向田さんに興味を持たれたのだろう。だがこれも考えようによってはかなりおかしい(これは笑えるという意味)ことである。そう思っていたら、案の定思った通りの愚痴が聞こえてきたのでやっぱりそうかとほくそ笑んだ。

 向田さんの小説の本流は、身近な題材からの家族的な心のひだを描いたものである。男と女のすれ違いや内に秘めた嫉妬のような情念が折々に顔を出す。その描きかたがうまい。いわば湿度の高い小説である。対して高島さんは博覧強記の学者肌、男と女に関しては朴念仁(失礼)と思われる。ご自身のその種のことは未だに一切書いていないがおそらく生涯獨身なのであろう。勉学に夢中でそっち方面にはまったく興味のなかった人とお見受けする。向田さんも戸籍的には生涯獨身だったが、こちらはあれこれと色々あったらしい。男女の機微を書くのは十八番である。そんな対照的な二人がひょんなことで結びついた。向田さんの物書きとして感覚を高島さんが認めたわけだが、作品内容的にはお二人が合うとは思えない。さてどうなることやらと思っていた。 向田さんの小説の本流は、身近な題材からの家族的な心のひだを描いたものである。男と女のすれ違いや内に秘めた嫉妬のような情念が折々に顔を出す。その描きかたがうまい。いわば湿度の高い小説である。対して高島さんは博覧強記の学者肌、男と女に関しては朴念仁(失礼)と思われる。ご自身のその種のことは未だに一切書いていないがおそらく生涯獨身なのであろう。勉学に夢中でそっち方面にはまったく興味のなかった人とお見受けする。向田さんも戸籍的には生涯獨身だったが、こちらはあれこれと色々あったらしい。男女の機微を書くのは十八番である。そんな対照的な二人がひょんなことで結びついた。向田さんの物書きとして感覚を高島さんが認めたわけだが、作品内容的にはお二人が合うとは思えない。さてどうなることやらと思っていた。
つい最近の『お言葉ですが…』にその辺のことが書かれていた。その本を編むために、高島さん、向田さんの作品をあれこれ読んだらしい。いや読まざるを得なかった。するとその中に「亭主の愛人がどんな女か、女房が妾宅に出かけて盗み見るシーン」というのがあったそうな。そのことに関し、「まったくこんなのばかりでイヤになる。亭主の妾を女房が見に行くものだろうか」と書いている。見に行くよね。世の中そんなものだ。向田さんの作品は「亭主に愛人がいるらしい。そのことを女房はきづいている。でも本妻はわたしなんだとプライドの高さでしらんふりをしている。動じない。だけどやっぱり気になって、そっとどんな女か見に行く」というあたりの心の動きがおもしろいわけで、それを「そんなバカなことをするか!」とうんざりしてしまうのだから、高島さん、本質的に向田さんとは合っていない。大好きなお二人のかみ合わない具合を、楽しく拝見させてもらった。
 久世光彦の「向田邦子との二十年」を読んでいたら、向田さんと長年のつきあいであり親しかった久世さんが、向田さんも男と女のどろどろした性的にことに関しては何も知らなかったのではないかと書いていた。(09/12/5) 久世光彦の「向田邦子との二十年」を読んでいたら、向田さんと長年のつきあいであり親しかった久世さんが、向田さんも男と女のどろどろした性的にことに関しては何も知らなかったのではないかと書いていた。(09/12/5)
---------------
 餘談ながら、七八年前に親しくなり、やがて疎遠になってしまった中小出版社の社長がいる。学生運動家出身で大江の信奉者だった。その彼が向田さんの文章をどこがいいのかわからないと否定していたのが印象的だった。彼はぼくに自分と一緒に大江を賛美し向田さんを否定するような感覚を望んでいた。疎遠になったのは自然だった。大江の乾いたセメントのような文章を好む人は、向田さんの湿気の強い文章は理解できまい。 餘談ながら、七八年前に親しくなり、やがて疎遠になってしまった中小出版社の社長がいる。学生運動家出身で大江の信奉者だった。その彼が向田さんの文章をどこがいいのかわからないと否定していたのが印象的だった。彼はぼくに自分と一緒に大江を賛美し向田さんを否定するような感覚を望んでいた。疎遠になったのは自然だった。大江の乾いたセメントのような文章を好む人は、向田さんの湿気の強い文章は理解できまい。
逆にまた出久根達郎さんが自分の好きな人百人を集めたような本(後日註・調べたら『百貌百言』文春新書でした)で、向田さんのことを「突然現れていきなり名人」のように絶賛していたのは嬉しかった。出久根さんは、それ以前に、吉本ばななの文章に対して、「何も感じない。その原因を探していたら、文章そのものが死んでいることに気づいた」とスゴイことを書いていた。吉本ばななが大スターの時だから、ああいう断言は凄いなあと感激したものだった。非力な人間は自分の感覚を信じて生きようと思いつつ常に不安と共にいる。信じている人が自分と同じ事を堂々と発表してくれるとありがたいと思う。
 ところでATOKは「出久根」という苗字が出なかった。これは私の田舎の苗字なので私には子供の頃よりなじみがある。出ないので驚いた。珍しい難読苗字かもしれないが直木賞作家なのだから辞書に入れるべきだろう。毎度の愚痴をまたここで言ってもしょうがないが、若手タレントのフルネームを一発で変換させたり、「記者が汽車で帰社する」なんてのを一発変換すると自慢するより、出久根さんのような直木賞作家や、談志、志ん朝、小さんのような著名な落語家や大相撲の力士等の名前を変換できるようにすべきではないのか。どう考えても、数年後にはどうなっているかわからない十代のタレントの名前が一発変換されて、十年以上相撲を取っている力士や、それこそ何十年も活躍している落語家の名前が変換できないのはあきらかにおかしい。 ところでATOKは「出久根」という苗字が出なかった。これは私の田舎の苗字なので私には子供の頃よりなじみがある。出ないので驚いた。珍しい難読苗字かもしれないが直木賞作家なのだから辞書に入れるべきだろう。毎度の愚痴をまたここで言ってもしょうがないが、若手タレントのフルネームを一発で変換させたり、「記者が汽車で帰社する」なんてのを一発変換すると自慢するより、出久根さんのような直木賞作家や、談志、志ん朝、小さんのような著名な落語家や大相撲の力士等の名前を変換できるようにすべきではないのか。どう考えても、数年後にはどうなっているかわからない十代のタレントの名前が一発変換されて、十年以上相撲を取っている力士や、それこそ何十年も活躍している落語家の名前が変換できないのはあきらかにおかしい。


 上の写真は『QXエディター』で書いている小説の画面。黒バックに白文字は「長文を書く場合、最も目が疲れない設定」として有名で、MSーDOS時代からずっと使ってきた。いわば古女房のようなものなのだけど、色々な設定に浮気した結果、やっぱりおまえがいちばんとなり、これに落ち着いている。まず間違いなく、今後もこれだろう。 上の写真は『QXエディター』で書いている小説の画面。黒バックに白文字は「長文を書く場合、最も目が疲れない設定」として有名で、MSーDOS時代からずっと使ってきた。いわば古女房のようなものなのだけど、色々な設定に浮気した結果、やっぱりおまえがいちばんとなり、これに落ち着いている。まず間違いなく、今後もこれだろう。
見づらいが、最下段に赤字が見える。「原稿用紙換算枚数」の表示。便利で助かる。
 縦書きの出来るエディターは、最初が『WZエディター』で、次に『QXエディター』、昨年あたり、シェアウェアの『O’sEditer』を知り、購入してみた。結局今、『QXエディター』を使うことが一番多い。あ、フリーソフトの「EMエディター」なんてのも使った。フリーながらたいした能力だった。ああいうソフトを作り、無料で解放する人の心意気には、心から感謝し尊敬している。 縦書きの出来るエディターは、最初が『WZエディター』で、次に『QXエディター』、昨年あたり、シェアウェアの『O’sEditer』を知り、購入してみた。結局今、『QXエディター』を使うことが一番多い。あ、フリーソフトの「EMエディター」なんてのも使った。フリーながらたいした能力だった。ああいうソフトを作り、無料で解放する人の心意気には、心から感謝し尊敬している。
といって長年使っている『WZエディター』をまったく使わなくなったかというとそういうものでもない。これらのソフトはいくつもの書式を記録しておき読み出せるのだが、たとえば私の場合、週刊誌に書いていた「一行13字、縦書き、75行、禁則処理なし」というのがあった。こういう特殊な形式をいちばん愛用している『QXエディター』の書式のひとつとして登録しておき、毎度読み出し切り替えるのは面倒である。で、『WZエディター』にこの設定をし、その週刊誌エッセイ専用にしていた。複数のソフトを使うことにはこういう利点もある。
その仕事が終ると、その設定を解除する。何年も続いてきた仕事が終ったのだなあと確認し、ふと寂しくなるのはこんな時である。
エディターということでは有名度一番かもしれない「秀丸エディター」というのは、縦書きが出来ないし、作者も対応するつもりはないと宣言していたので(つまりご本人が縦書きを必要としないプログラマー出身の人なのだろう)、こちらも最初からまったく興味がなかった。

 上の写真は『O’sEditer』のもの。これは「秀丸」とは逆に、シナリオライターの人が自分が必要とする縦書きエディターを開発しようとしたものだから、縦書き表示、印刷等、かゆいところに手が届くように出来ていてまことにすばらしい。ルビまで振れる。ただ多くの商業文章を前記のように「黒画面に白文字」で長年書いてきた私には、今更原稿用紙設定は必要なかった。放送原稿を書いていた頃は局指定の原稿用紙に書いていたし、それこそ物書きなら誰もがあこがれ、そして実行するらしい「自分の名入り原稿用紙」なんてものに興味をそそられたこともあったのだが、いつのまにか普通紙のA-4に印刷することが日常となっていた。今も『O’sEditer』は大好きなので、『QXエディター』と併用しているが、カスタマイズの点で『QXエディター』のほうが自由度が高く、二番手の位置である。 上の写真は『O’sEditer』のもの。これは「秀丸」とは逆に、シナリオライターの人が自分が必要とする縦書きエディターを開発しようとしたものだから、縦書き表示、印刷等、かゆいところに手が届くように出来ていてまことにすばらしい。ルビまで振れる。ただ多くの商業文章を前記のように「黒画面に白文字」で長年書いてきた私には、今更原稿用紙設定は必要なかった。放送原稿を書いていた頃は局指定の原稿用紙に書いていたし、それこそ物書きなら誰もがあこがれ、そして実行するらしい「自分の名入り原稿用紙」なんてものに興味をそそられたこともあったのだが、いつのまにか普通紙のA-4に印刷することが日常となっていた。今も『O’sEditer』は大好きなので、『QXエディター』と併用しているが、カスタマイズの点で『QXエディター』のほうが自由度が高く、二番手の位置である。
 長年の『一太郎』ユーザーだが、物書きは字を書くだけでいいので──見出しを大きなポイントにしたり、カラフルな表を作ったりする必要がない──Version5、一太郎ユーザーで言う五太郎ぐらいからもうまったく使っていない。ATOKは買い続けているが。 長年の『一太郎』ユーザーだが、物書きは字を書くだけでいいので──見出しを大きなポイントにしたり、カラフルな表を作ったりする必要がない──Version5、一太郎ユーザーで言う五太郎ぐらいからもうまったく使っていない。ATOKは買い続けているが。

↑一太郎の縦書き画面
 MSーDOS時代にもうワープロソフトは卒業していた。それはすなわちその頃にもう職業物書きになっていたということである。もしも私が普通の勤め人で、趣味の会報のようなものを作っていたなら、DTPには当時から興味を持っていたから、今頃一太郎使いの名人になっていたように思う。 MSーDOS時代にもうワープロソフトは卒業していた。それはすなわちその頃にもう職業物書きになっていたということである。もしも私が普通の勤め人で、趣味の会報のようなものを作っていたなら、DTPには当時から興味を持っていたから、今頃一太郎使いの名人になっていたように思う。
このころ愛用していたエディターソフトは、テグレット技術開発の「彰子の書斎」だった。と、またまた思い出のソフトウェア話になってしまうので先を急ぐ。だいぶ本題からズレてしまった。
 エディターの話をする場所ではなかった。好きなんだよなあ、こういうソフトウェアの話が。中でもエディターには様々な思い込みがある。きちんと本題にもどろう。 エディターの話をする場所ではなかった。好きなんだよなあ、こういうソフトウェアの話が。中でもエディターには様々な思い込みがある。きちんと本題にもどろう。
本題は、「私にとって縦書きとは何か、横書きとは何か」である。縦書き横書きを何で書いているかという話ではなかった。

 このままだといつまで経っても本題にたどり着けないような気がしてきたのでいきなり結論から行こう。結論を書いてしまえばいかな私でも脱線は出来まい。 このままだといつまで経っても本題にたどり着けないような気がしてきたのでいきなり結論から行こう。結論を書いてしまえばいかな私でも脱線は出来まい。
私にとって縦書きとは「商業用文章」なのである。二十七で初めて文章を書いて金をもらってから今に至るまで、私は一貫して「金をもらう文章は縦書き」でやってきた。普段の文章は手紙からメモに到るまで横書きである。この「金をもらう文章は縦書き、私的なことは横書き」というのは、私のアイデンティティとしてかなり強烈に刷り込まれている。
もちろん例外はあった。コピーライターとしての商業コピーは横書きだったし、横組みの広告誌や雑誌にはなんどか横書きで書いている。最近の放送原稿は横書きで出してくれと指示されている。
私は縦書き支持者だけれど、アルファベットの横文字馬名や数字の多い競馬雑誌などは横組みのほうが適していると思う。決して横組みを否定しているわけではない。
 これは強烈な縦書き支持者である高島さんもそうらしく、『お言葉ですが…』のこの項目で、そのことを書いていた。高島さんが腹立つのは、「横書きのワープロで書いた原稿を、日本の本は縦組みだからと縦書きで出してくるエセ縦書き」であるという。つまり縦書きの文章からのみ感じられる「縦書きの思想」のようなものがあり、それのないものを無理矢理形式的に縦書きにしてくれるな、というのが高島さんの主張なのだ。この感覚は、高島さんと比して自分も同じだなどと言うのはおこがましいが、私にも理解できるものになる。 これは強烈な縦書き支持者である高島さんもそうらしく、『お言葉ですが…』のこの項目で、そのことを書いていた。高島さんが腹立つのは、「横書きのワープロで書いた原稿を、日本の本は縦組みだからと縦書きで出してくるエセ縦書き」であるという。つまり縦書きの文章からのみ感じられる「縦書きの思想」のようなものがあり、それのないものを無理矢理形式的に縦書きにしてくれるな、というのが高島さんの主張なのだ。この感覚は、高島さんと比して自分も同じだなどと言うのはおこがましいが、私にも理解できるものになる。
縦書きの思想がわかるということは即ち横書きの思想も理解できるということであり、高島さんは横書きで書かれた本に対し、実例を挙げて「横書きの名文」と褒めている。今後、横書きで書かれ、横組みで出版される小説類も増えることだろう。私は読む気にはなれないが。「横書きの思想」は私にはわからない。
私の場合、横組みというのは「研究レポート」や「報告書」であり、勉強や資料にはなっても「娯楽」にはなり得ない。極端な話、『週刊文春』や『週刊新潮』はもちろん、『週プロ』のようなプロレス週刊誌でも、横組みになったら私は読むのを止めるだろう。脳みその回路がそういうふうに出来てしまっているので受けつけないのだ。日本の出版物のすべてが横組みになってしまったら、それはそれであきらめるしかないが、うまくとけこめるまでに私は十年はかかるだろう。
---------------
 「競馬ブック」という関西発刊の競馬週刊誌がある。私は今までただのいちども読んだことがない。いやそれは嘘か。買ったことがない。数回は読んでいる。これも横組みのせいである。それは「資料」にはなっても「娯楽」にはならないからで、私にとって競馬週刊誌は娯楽のものだから、楽しめない横組みでは買う気になれないのである。 「競馬ブック」という関西発刊の競馬週刊誌がある。私は今までただのいちども読んだことがない。いやそれは嘘か。買ったことがない。数回は読んでいる。これも横組みのせいである。それは「資料」にはなっても「娯楽」にはならないからで、私にとって競馬週刊誌は娯楽のものだから、楽しめない横組みでは買う気になれないのである。
何年か前に産經が「Gallop」という新競馬週刊誌を出し、全社員に大入り袋が配られるほどの大ヒットになった。「競馬ブック」の寡占状態だったところに一石を投じたわけだが、支持者の多くは「競馬ブック」の横組みに反発を感じていた読者だったことだろう。
「競馬ブック」というのは競馬新聞としてもユニークな横組みなのだが、ユニークというのはあくまでも関東側からの発想で、なにしろ関西では寡占状態のダントツ売上げの新聞だから、関西人は逆に関東に来ると縦組み競馬新聞の多いことに戸惑うらしい。いわゆる標準語をしゃべって関西臭さを隠している人も、手にしている新聞を見れば関西人であることがすぐわかる。競馬新聞というのもなじんでしまうと変えられないものなのだ。
---------------
 結局私の縦組み支持へのこだわりは、この競馬新聞愛好レヴェルなのである。長年、私的なものは横書き、お金をいただくものは縦書きと使い分けてきた。その慣れ親しんだ感覚から抜け出せないのだ。根底には、子供の頃から読んできた小説類がすべて縦書きという刷り込みもあるだろう。テキストエディターを縦書きにセットするとその気になるのである。条件反射だ。 結局私の縦組み支持へのこだわりは、この競馬新聞愛好レヴェルなのである。長年、私的なものは横書き、お金をいただくものは縦書きと使い分けてきた。その慣れ親しんだ感覚から抜け出せないのだ。根底には、子供の頃から読んできた小説類がすべて縦書きという刷り込みもあるだろう。テキストエディターを縦書きにセットするとその気になるのである。条件反射だ。
私は長年その感覚を、ヤクザな男から逃げられない悲しい女の性や、競馬場に入った瞬間、金銭感覚が麻痺してしまう己の愚かさと同一視していた。縦書きに対する多少のこだわりと、そのこだわりに対する誇りを幾分かはもっていたにせよ、私は縦書きを愛好する自分を決して肯定的に見ていたわけではない。むしろ横組みを楽しめない自分を不器用な奴と軽んじていたぐらいだ。ところが最近になってやっとこれは使い道のある習性だと思い至った。
怠け心を排除し、よおしやるぞと、やる気を出し、シャキっとして仕事をしようとするとき誰もがすることは、部屋の掃除であり(笑)、整理整頓した机に向かうことであろう。まあすくなくとも私はそうだ。部屋を掃除し、冒頭の写真にあるようなデスクトップで、大型液晶画面を見ながらキイボードに向かう。かたわらにはやる気を出すという赤いトルマリンリンゴや、精神統一するためのお香なども焚かれている。しかしながら首と腰の持病もあり、机に向かっても、私はすぐにため息をつき、飽きてしまうのである。首と腰以前の問題のような気もするが。
机を離れ、クッションに頭を乗せて寝転がる。いわゆるラッコ状態で、腹の上にノートパソコンを拡げ、将棋などを始めたりする。これではいかんと思いつつ……。
ところが、寝転がった行儀の悪い状態でも、私はテキストエディターを縦書きにすると、「さあ仕事だ!」とシャキっとするのである。習慣とはおそろしい、いやすばらしい。そのことに気づいて、私はだいぶ気が楽になった。デスクトップに向かってもすぐに飽きてしまう自分に、かなり本気の危機感を持っていたのである。でもその行儀の悪さにさえこだわらなければ、ラッコ状態なら私は何時間でも仕事が出来るし、行儀は悪くても、縦書きでさえあれば、精神的には直立不動なのである。精神の背筋はピンと伸びている。
「縦書きは仕事」「縦書き状態にセットしたら仕事モード」という長年の習慣が、今後の虚弱体質オヤジのホソボソとした執筆生活を助けてくれるのは間違いない。
「縦書きと横書き」と題して延々と書いてきたが、唯一書きたかったのはこの、縦書きにすると条件反射でキチンとする自分についてだった。
(書こうと思い立ってから実に三年。やっと書き終ったのは02年10月10日の朝七時、異国景洪のホテルだった。)

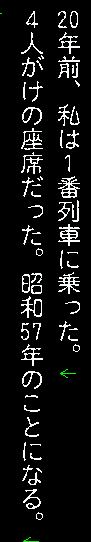  書きたいことは全部書いたつもりだったが大切なことを思い出した。なんだかこんな感じで、この項目はまた書き足しがありそうである。 書きたいことは全部書いたつもりだったが大切なことを思い出した。なんだかこんな感じで、この項目はまた書き足しがありそうである。
昨年、友人が出版した本が贈られてきた。そこでは左の例のように縦書きの文章でありながら、「20年前」「1番列車」のように、数字はすべてアラビア数字に統一されていた。もちろんこの文章は私がとりあえず作ったいいかげんなものである。まあ、こんな感じ、という例である。
その出版社で出している雑誌ではすべてそのように表記されているので、もしかしたら単行本でもと懸念されたことではあったが、私には何とも理解できないことだった。また友人がゲラを読みながらこれを訂正しなかったことも納得し難かった。その出版社では数字はすべて算用数字に統一しているらしい。雑誌類の原稿でも縦書きの「20年前」だから、そこに連載していた彼の文章が本になってそうなのは当然とも言えるのだが。
さすがに「一緒に」とか「一気に」は直してなかったが、これももしかしたらその内、「1緒に」「1気に」になるのではないかと思わせるほどの徹底ぶりだった。友人には悪いが私はその本を読む気になれなかった。あまりにもその表記が気になってならないからである。
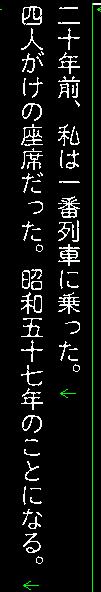  私の望むのはもちろん隣にあるような表記である。これを常識と思われるかたも多いと思うが、時代は今、上記のようになりつつある。私は自分の小説が縦書きなのに「20年前」と半角算用数字で統一されるなら出版を拒む。といっても「昭和57年」ぐらいはしかたないかと妥協するし、西暦に関しては「82年」のほうが雰囲気がいいと思っているから、なんでもかんでも漢数字にこだわるわけではない。でも日本語の縦書き小説で「にじゅうねんまえ」と書くとき、それは断じて「20年前」ではなく「二十年前」だと思っている。これは譲れない。 私の望むのはもちろん隣にあるような表記である。これを常識と思われるかたも多いと思うが、時代は今、上記のようになりつつある。私は自分の小説が縦書きなのに「20年前」と半角算用数字で統一されるなら出版を拒む。といっても「昭和57年」ぐらいはしかたないかと妥協するし、西暦に関しては「82年」のほうが雰囲気がいいと思っているから、なんでもかんでも漢数字にこだわるわけではない。でも日本語の縦書き小説で「にじゅうねんまえ」と書くとき、それは断じて「20年前」ではなく「二十年前」だと思っている。これは譲れない。
 お隣の漢字の本場中国では文章は横書きに徹し、数字も算用数字で統一されている。暦は西洋歴だ。「20年前の8月、1982年のことである」のような表記になっている。それはそれで、ひらがなカタカナのない漢字だけの国としてほんとに苦労しているから、すこしでも簡便にするために仕方がないと思う。横書きだしね。 お隣の漢字の本場中国では文章は横書きに徹し、数字も算用数字で統一されている。暦は西洋歴だ。「20年前の8月、1982年のことである」のような表記になっている。それはそれで、ひらがなカタカナのない漢字だけの国としてほんとに苦労しているから、すこしでも簡便にするために仕方がないと思う。横書きだしね。
機会があったら「中国のアルファベットを子供に覚えさせる一覧表」の写真を掲載したい。ABCの発音を中国の子供に教えるものだが、アルファベットの横に実に難しい漢字が書かれていて苦笑してしまう。CとかOのような簡単な文字の発音を教えるのに、音を表す文字が漢字しかないから、難しい字が添えられているのである。あれを西洋人が観たら「テリブル!」とでも言うのではないか。だって一筆書きのアルファベットの発音を現すのに三十画ぐらいの難しい漢字が添えられているのだ。けっこうこれって滑稽だ。漢字を輸入しつつ自分たちに便利なようにひらがなカタカナを発明してしまった日本人の賢さがよくわかる。
---------------
  今回、中国の子供の作文ノートを買ってみた。日本の原稿用紙に似た作りの横書きである。中国はそこまでもう徹底している。水墨画の文字でもなければ縦書きを見ることはない。漢字だとか縦書きだとかの同じ発想で中国と日本はもう語れないだろう。(本来、「中国、朝鮮、日本が同じ漢字文化圏という発想がそもそも間違いである」という論議はまたの機会として。) 今回、中国の子供の作文ノートを買ってみた。日本の原稿用紙に似た作りの横書きである。中国はそこまでもう徹底している。水墨画の文字でもなければ縦書きを見ることはない。漢字だとか縦書きだとかの同じ発想で中国と日本はもう語れないだろう。(本来、「中国、朝鮮、日本が同じ漢字文化圏という発想がそもそも間違いである」という論議はまたの機会として。)
 横書きだと算用数字にも抵抗が少ない。「20年前」も、横書きならそれはそれでいいように思う。私もこのホームページでは多用している。「1984年」と書く。それは「千九百八十四年」とか書くと重く感じるからだ。もちろんそれを必要とする縦書き小説ではそうする。 横書きだと算用数字にも抵抗が少ない。「20年前」も、横書きならそれはそれでいいように思う。私もこのホームページでは多用している。「1984年」と書く。それは「千九百八十四年」とか書くと重く感じるからだ。もちろんそれを必要とする縦書き小説ではそうする。
 『週刊アサヒ芸能』に三年間連載して一度も不愉快な思いをしたことがなく、あそこの編集部には心から感謝していると何度か書いているが、こういうことに関してもそうで、私が獨自の漢字使いをしても、「作家さんの漢字の使いかたは尊重します」とそのままで通してくれた。逆にまたそれがありがたかったので無茶なことはなるべくしないようにした。あそこでダメだったのはキチガイの類だけである。あれは異常に神経質だった。狂うという漢字を使わせてくれなかった。「馬券狂」ですらダメだった。それだけキチガイの読者は怖いのだろう。 『週刊アサヒ芸能』に三年間連載して一度も不愉快な思いをしたことがなく、あそこの編集部には心から感謝していると何度か書いているが、こういうことに関してもそうで、私が獨自の漢字使いをしても、「作家さんの漢字の使いかたは尊重します」とそのままで通してくれた。逆にまたそれがありがたかったので無茶なことはなるべくしないようにした。あそこでダメだったのはキチガイの類だけである。あれは異常に神経質だった。狂うという漢字を使わせてくれなかった。「馬券狂」ですらダメだった。それだけキチガイの読者は怖いのだろう。
さっき川端康成の『雪国』を読んだのだが、「盲」「白痴」「気違い」という現在では使えない言葉が目についた。今、IMEではメクラは出ないので「盲人」と打って出した。つまり「盲」という漢字が差別用語なのではなく「メクラ」という音(おん)に問題があるわけだ。
先日「こびと」が出ないと知った。「しょうじん」だと出るから反って笑ってしまう。あ、この「反って(かえって)」は川端康成の使いかたを真似てみました(笑)。
 そのうち縦書きでも「20年前」があたりまえの世の中になるのだろうか。なんとも納得しがたいのだが、それがすぐそこまで来ているのもまた確かなのだ。 そのうち縦書きでも「20年前」があたりまえの世の中になるのだろうか。なんとも納得しがたいのだが、それがすぐそこまで来ているのもまた確かなのだ。
(02/10/19 景洪)


上記は2002年の10月。関連したこれを書くのは2007年の6月だから5年4ヶ月ぶりの続篇である。と、早くも算用数字を多用してしまった。
その間に『週刊文春』は激しく変動し二十年以上愛読してきた私は今ではいっさい読まなくなった。いや立ち読みはしているから買わなくなったが正しいか。でも毎週発売と同時に購入して隅から隅まで読んでいたのと比べると、冷たい視線で目次を眺め、目にとまったものをふたつみっつ皮肉な視線で読むぐらいだからかつてとはちがう。連載エッセイのハヤシマリコやシーナマコトも一切読まなくなった。編集長によって雑紙が変ると連載ものに対する視点も変るようだ。というかさすがに飽きていたのだが。
高島先生の『お言葉ですが…』も不本意な形で連載が終了してしまった。でもインターネットで再開された。実現してくれたのは草思社である。ありがたいことだ。
---------------
草思社Webでの『お言葉ですが…』第八回は「新聞の算用数字」。これは以前にも一度書かれたテーマである。縦書き文章である新聞が算用数字を多用する文章の醜さについてだ。
以前にも書かれたテーマであるし、私も上記にまとめてあるのでさしてつけたすほどのこともない。全面的に高島さんを支持する。
あらためて思ったのは「縦書き 横書き」についてである。今回高島さんも最初に「この文章は、パソコン画面では横書きで出るらしいが、原稿は原稿用紙に縦書きで書いております」との断り書きからはじめている。要は「縦書き文章における算用数字の使い方」である。
私は元々西洋的なものがきらいだから(正しくは西洋的なものが大好きな日本人が大嫌い、なのだが)日本語の文章に算用数字をつかうのをよしとしない。しかしいつしか多用するようになっていた。その原因はひとえに「横書き」である。漢字の本家中国は新聞なども文章中の数字はすべて算用数字に統一されている。それは横書きだからだろう。縦書きに用いるとマイニチシンブンのようになって不自然だ。しかし今回高島さんが取り上げているのは産經新聞である。私はいま、ネットの横書き新聞しか読まないから無関係だが、縦書きの紙の新聞ではその問題が顕著なようだ。
---------------
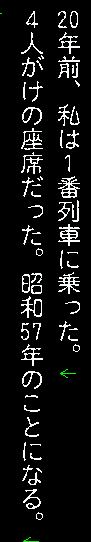 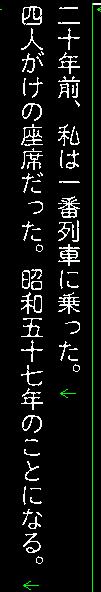 左は上記「縦書き 横書き」に用いた私の作った図?である。縦書きでこういう文は書きたくないと思う。いまマイニチシンブンはこうなっているわけだ。 左は上記「縦書き 横書き」に用いた私の作った図?である。縦書きでこういう文は書きたくないと思う。いまマイニチシンブンはこうなっているわけだ。
ただこれも「20年前、私は1番列車に乗った。4人がけの座席だった。昭和57年のことになる」と横書きにすると違和感がだいぶ減る。さすがに「1番列車」はやらないが、このホームページの文章で私は「20年前」「昭和57年」を多用している。特に私的な日記では、「にじゅうねんまえ」を変換する場合、半角キーを押して「20」を表記し、それからかなにもどして「ねんまえ」を打つのが習慣になっていた。
これはインターネットを利用するものとして、ログインするときのユーザーネームやパスワード等、すべて半角英数字が基本なのだから、PCを利用するものとしてしかたないともいえる。
が、なにも私的な日記でまで使う必用はない。
言いわけとして、ネット用の横書き商業競馬文章が、そういうふうに書式統一されていることがある。そういう書式が一般的だから、ついつい私的な文もそうしてしまいがちだ。
ネット用に限らずとも、競馬文章の場合は年代と数字が連発されることが多い。そもそもそういう文章は横書きと算用数字が適しているのである。今年春(2007年)から競馬週刊誌『Gallop』が横書きになった。それは時代に即した流れであり、先輩横書きの「競馬ブック」に先見の明があったのだ。
私は数字とアルファベットを多用する横書き文章の場合、算用数字の使用はしかたないと思う。むしろ半角アルファベットの人名等と並んで全角の漢数字があったら異様だ。仕事の競馬文章は別にしても、このホームページに書く音楽であれ映画であれ、それらはアルファベットと算用数字を多用する文章である。1996年をいちいち千九百九十六年と書くのは不適切だろう。しかたないと思う。いや、横書きのそういう文章では適切と思う。
私は縦書き可能のテキストエディターを常用するから原稿用紙設定の大きなフォントで縦書き文章を書くことが多い。そこには「縦中横」というマイニチシンブンのような表記をする機能があるのだが今は使わないようにしている。当初、この機能には感謝した時代もあった。いま「20年前」とあえて縦書きで書く理由はない。「二十年前」でいい。
高島さんが提起するこの算用数字の使用法はあくまでも「縦書き 横書き」の問題なのだ。今回不納得の使用例としてあげている産經新聞の使用法も縦書きの新聞だから醜い。
ざっと見て最も見苦しい、あるいは無茶だと思うのは、縦見出しで四ケタの数を横並びにして一字分とすることである。「5万6000基開始」とある。6とおしまいの0とは横にはみ出している。記事のなかでもそうするのかと思えばそうではなく、「全国の約5万6000基」と縦に並んでいる。しかも「約」である。ぴったり一のケタまでゼロなのではなく、だいたい五万六千前後なのである。「六千」と書けばだいたい六千だが、「6000」では一のケタまでゼロがならんだ、ぴったり六千という数をあらわすことになってしまう。
この産經新聞の表記の見にくさ、醜さは横書きだとそれほど伝わってこない。それがこの問題の本質のように思う。
縦書きなのだからやはりこの場合は「五万六千」がベストだろう。私は自分の日記だと「5万6千」と書いたりする。馬券の収支など(笑)。この場合なぜ56000にしないかというと、私は算用数字の桁が一瞬にして読めないからである。たかが56000でも、「え~と、5万 6千だよな」と時間がかかる。もっともっと大きくなると、「一、十、百、千」とゼロを数えねばならない。
新聞の場合は各社の規定があり、それにしたがうからこんなみっともない表記になる。でも産經もなあ、「五万六千」でいいだろうに、なんでこんな表記をするのか。理解に苦しむ。
漢字が日本に入ってきたとき日本語とぶつかってたいへんだったそうだ。落ち着くまで長い月日が必要だった。いまインターネットの普及により一気に横書きが優勢になってきたから、あらためて数字やアルファベットを考え直す時期なのだろう。ただもう横書き文章における英数字、アルファベットは結論が出ていると思う。残された問題は高島さんが提起しているような縦書き文章における算用数字の用い方、のみなのである。
============================================
Web草思の『新・お言葉ですが…』がしばらく休載だという。以下は高島さんのことば。
おわび。
筆者現在心神状態甚だ不振につき、この連載しばらくお休みさせていただきます。勝手の段深くおわび申しあげます。
心身ではない。心神なのである。体だとそこいら中に故障を抱えていて「病院のカードの数ならまけない」と冗談を言う先生のことだからかえって安心するのだが、どうやら精神が不調らしい。いまの先生には大好きなお母さんももういらっしゃらないし、心を病むほどの憂慮はないと思うのだが、どうなさったのだろう。心配である。
月二回の連載が「しばらくお休み」とはどれぐらいだろう。先生の恢復を心から願っております。

|