| 03/4/29 | 唄いたくない歌 過日のカラオケで年下の友人(といっても四十代)がなぜか70年代フォークの「教訓Ⅰ」を歌い始め、うまく歌えずぼくにマイクを回してきた。彼としてはそういう歌がぼくの十八番であると思いこんでのサービス精神だったのかもしれない。いい迷惑だった。 自分のよく知っている歌を友人がうまく歌えないというのはいらだつもので、ぼくは加川良のそれなど耳をふさぎたくなるほど聞きたくなかったのだが、ある程度そうじゃないそうじゃないといういらだちが顔に出ていたのかもしれない。うまく歌えない彼にたのんますとばかりにマイクを回されると、思わず上手に歌ってしまったのだった。なにしろよく知っている。 メロディには作者の癖が出る。唄うほうにも歌い方のくせがある。だから「よく知らない歌を、自分の感覚で歌う」と、作者の癖と歌い手の癖が微妙にズレて、おもしろい。ヘンな歌になる。ぼくの唄うカラオケの九割方は原曲と違う。ほとんどうろ覚えの曲を自分流で歌っている。一応音楽をやっていたので、メロディの流れとコードをつかめるから、外してはいないが、譜割りは獨自のものとなっている。基本に忠実な人が聞いたら、なんか違うなあと気持ち悪くなるだろう。 正しく唄う一割はなにかといえば、「この歌いいから覚えたい」とCDを聞いて覚えた最近の曲である。最近の曲はそういう作者獨自の譜割りを、かなり意図的であろうが、常識的な譜割りから外して創っているから、正しく覚えないと唄えない。 友人と行ったスナックで、見知らぬオジサンが「涙そうそう」を上手に唄っていた。ぼくはあの歌を聞き流しでしか知らないので、モニターの歌詞を見つつ初めて真剣に聞いてみた。それでしみじみ思ったのだが、常識的な譜割りを外しまくった作り方をしているということだった。「いか天」に出ていた沖縄のバンドBeginが作った曲とは知っていた。あれを二三回聞いて正確に唄うのはぼくには絶対に無理だ。その代わり、あの獨特の譜割りには、百回聞いて覚えて、正確に唄えるようになったとき、達成感にも似た快感があるのだろう。 「涙そうそう」などと比べたら時代的な差もあり、「教訓Ⅰ」なんてのは作者の癖といってもかわいいものだった。それでもやはりうろ覚えでは唄いこなせないらしく、そのままぼくが最後まで唄った。 「死んで お国のためといわれるより 生きて バカだと言われましょうよね あわてるとついふらふらと お国のためなのといわれるとね 青くなって尻込みなさい 逃げなさい 隠れなさい」等の歌詞を歌うのがいやでいやでたまらなかった。だけどこうなったのも自業自得なのだと、これは避けては通れない道なのだと、鉛の棒を飲み込むような気持ちで唄いきった。いやな歌を歌うとあんなにも気分が悪くなるのだと初めて知った。だっていやな歌なんて唄うはずもないから。 ぼくは学生時代、この歌を粋がって歌ったことがある。その過去は消せない。なにしろ上記のように歌詞がすらすら出てくるぐらい未だに覚えている。 そこから「なにを学ぶか」がたいせつなのだ。その後の「学んだものをどう活かすか」のほうがより重要ではあろうが、まずは「そこから逃げず、しらんふりしない」ことを貫きたい。 たとえ中国の奥地でどんなに活字に飢えようと絶対に読むことのない朝日新聞だが、あそこには「過去の所行をしらんふりする醜さ」を教えてもらった。それだけはしたくない。 朝日の名物記者だったホンダカツイチの研究サイトがある。彼がいかに状況に応じて都合よく言い分けているかが、弁明不可能なほど、きっちりと証明されている。なにしろ出版物という物証があるのだから逃げ隠れは出来ない。彼はしらんふりして逃げている。骨の髄まで朝日である。 いろいろと思うことの多いカラオケの夜だった。 |
| 03/10/9 | 永遠の音楽──チャーリー・パーカー  ほんの十年前の推理小説が携帯電話があったら成立しないと書きつつパソコンから「Charlie Parker──with
Strings」の音色に聞き惚れていたら、これって1949年のレコーディングなのだと思い出した。53年前である。なのにまったく色あせていない。未だにこれほど美しくアルトサックスを吹ける人はいまい。永遠なのである。そう考えたら、携帯電話の存在ひとつで存在価値の揺らぐ小説がきゅうにつまらなく思えてきた。 ほんの十年前の推理小説が携帯電話があったら成立しないと書きつつパソコンから「Charlie Parker──with
Strings」の音色に聞き惚れていたら、これって1949年のレコーディングなのだと思い出した。53年前である。なのにまったく色あせていない。未だにこれほど美しくアルトサックスを吹ける人はいまい。永遠なのである。そう考えたら、携帯電話の存在ひとつで存在価値の揺らぐ小説がきゅうにつまらなく思えてきた。また、最新のテクノロジーによるデジタル録音なんてのもどうでもよく思えてきた。素人の録音ですら32チャンネルなんてやる時代だが、このころなんて4チャンネルで、楽器の前にポンとマイク一本立てて録っていたようなものだ。それでいてこのレヴェルである。芸術は機械じゃない。 パーカーのこの作品は評価が分かれる。いわゆるウルサ型はスタンダードナンバーを万人に受けるように美しく演奏しているバード(パーカーの愛称。クリント・イーストウッドの作った映画「バード」は音楽に本物を使って話題になったものだった)を否定し、チャーリー・パーカーの作品としてこれを好む人をシロートとコバカにする。でもそれってあまりに心が狭いだろう。あの、この世のものとは思えないアドリブプレイ全開のヤク中のバードもすごいけど、まともなものをまともにできるそのことの凄味も認めないと。これも出来るからバードはすごいんだ。 |
| 03/10/16 | スタン・ゲッツとJJ  今夜は18℃。涼しいときにトロンボーンの音色はあったかくていい。この名盤、聞けば聞くほど感動する。これは当時の人気順からかスタン・ゲッツが前に来ているけどメインはJJだ。JJがすばらしい。トロンボーンでこんな速いパッセージを吹けるなんて天才としかいいようがない。すごい人だ。バックを支えているのがオスカー・ピーターソントリオだものなあ。最高だ。しかもホーン2本を前面に出し、脇役に徹している。プロ中のプロ。 今夜は18℃。涼しいときにトロンボーンの音色はあったかくていい。この名盤、聞けば聞くほど感動する。これは当時の人気順からかスタン・ゲッツが前に来ているけどメインはJJだ。JJがすばらしい。トロンボーンでこんな速いパッセージを吹けるなんて天才としかいいようがない。すごい人だ。バックを支えているのがオスカー・ピーターソントリオだものなあ。最高だ。しかもホーン2本を前面に出し、脇役に徹している。プロ中のプロ。1957年の10月19日と25日、シカゴとロスのライヴ。ちょうど46年前の今。モノラル録音。名品は永遠だ。こういうのを聞いてると多チャンネル録音とかデジタルうんぬんなんてのがどうでもいいことに思えてくる。 |
| 03/11/4 | Jazzの中のギター  ひさしぶりにジャズギターを聴いた。Joe PassとJohn Pisanoのツインギター、あとはベースとドラム。ホーンもピアノも入っていないピュアにギターメインの作品だ。ライヴ盤。 ひさしぶりにジャズギターを聴いた。Joe PassとJohn Pisanoのツインギター、あとはベースとドラム。ホーンもピアノも入っていないピュアにギターメインの作品だ。ライヴ盤。と書いて、なにいってんだ、ついこの間まで毎日Wes Montgomeryを聴いていたじゃないかと思い出す。なのになぜそんな感想をもったのかというと、このCDがいかにもギターらしいフレーズの連発するものだったからだ。つまりそれはWesのギターはギターフレーズじゃないってことを意味している。 JAZZの主役はラッパだ。一番手がトランペット、二番手がサックスになる。二番手のほうが表現力が大きく習うにも楽な楽器だから、多数決の原理でこれを王者という人も多いだろうが歴史的にペットが一番である。楽器の王様であるピアノですら配下においてしまうほどだ。 Wesはオクターブ奏法を用いて幅の広いホーンライクなギターフレーズを弾いた。いかにもギターソロらしいこちゃこちゃしたフレーズは弾いていない。だからずっとWesは聴いていたがギターと意識していなかった。それがハンマリングやプリングオフを多用したいかにもギターらしいフレーズの連発するこのアルバムを聴いてひさしぶりと感じた理由だった。 JAZZにおけるギターはつまらないなと思う。電気ギターが開発されるまでは、音が小さいからコードを弾いての伴奏楽器だった。ディキシーランド時代はバンジョーだった。やがて大音量が出せるようになりホーンと同じようにソロを取るようにもなる。だがジャズギターはブルースやロックにおけるチョーキングを邪道とした。ギターの最大の缺点はフレットで音が固定されていることにより微妙な音程が出せないことだ。その表現力不足が物足りなかった黒人はスライドギターを弾くことでカヴァーした。電気ギターの登場で大音量を出せるようになり、やわらかい弦によるチョーキングの多用でギターはロックシーンの花形楽器となる。Jazzにおいては、ピアノのように幅広く万能ではなく、単音でソロをとるにはホーンに比べて線が細く、微妙な表現ができないと半端な位置にいた。いや今もいる。これからもそうだろう。Jazz Musicにおけるギターの地位は低い。そこに甘んじてきた。せざるを得なかった。 その壁を破ったのが70年代後期に起きたクロスオーヴァーブームだった。そこではタブーとされていたディストーションを効かせたチョーキングを使ったフレーズが連発され、一躍ギターは新しいシーンの主役となってみせた。クロスオーヴァーやフュージョンシーンを、ぼくはJazzにおいてマイナー(=ロックにおいて大スター)だったギターが、その存在を主張したムーブメントとして記憶している。なにが交叉したのかなにが溶けあったのか。端的な答は「Jazzにロックギターを入れた」ではなかったか。一方、王者であるトランペットは確定している音色であるからこそシーンの中で迷走した。どう考えてもマイルスのフュージョンは失敗だろう。 ぼくのもっているJazzCDにはギターがかなりある。それはなぜだろう。そんなにギターの音色が好きなのか。そうでもない。その原因を突き詰めるとかなしい現実にたどりつく。ぼくの弾けるのはギター的な楽器(マンドリン、ウクレレ、バンジョー、ベース等)でしかない。何事においても評論家を嫌い常にプレイヤ志向のぼくは、Jazzにおいてもそうでありたかった。すると唯一まともに演奏できる楽器であるギター音楽をJazzにおいても追いかけるしかなかったのである。そのときには身びいきとして、自分の側のギターがフォークやロックでそうであるように、Jazzという分野でもスターであってほしいと願っていた。しかしそれから二十年ほどたち、我が身とは関係なく他人事風に俯瞰すれば、JazzMusicにおけるギターというのは、なんだかつまらない存在にしか見えないのだった。 ギターは、ロックでもブルースでもすばらしい。複雑なコードがメインのボサノヴァもいい。本家本元のクラシックは言うに及ばない。フラメンコも情熱的だ。ジプシーミュージックには泣きたくなる。演歌ギターの日本的情緒もなかなかのもんである。だけどJazzにおいてはギターは半端な楽器だ。唯一いいと思うのはコードで刻むバッキングになる。ということからも単音ソロには向いていないのだろう。 Jazzを聞き始めた当初、まさかこんなことを書くことになるとは思ってもいなかったが、これはこれで自分が弾ける楽器を身びいきする悪癖から抜け出た進歩ともいえる。抜け出たからこそ本質も見える。 中学のころ音楽部でホルンを吹いていた。友人のトランペットをいじったりしたし、今でも音階ぐらいは吹ける。でもやろうとは思わない。ひとりで吹く管楽器はむなしい。無用なこだわりを捨てて無の境地でみれば、これはまたこれでギターとはなんと魅力的な楽器であろう。ひとりで和音を奏でられ、獨奏ができ、伴奏ができ、携帯性まである。Jazzにおけるギターの地位を私欲なく見ることによって、その魅力を再確認できた気がする。 どうでもいい餘談として。 この「評論家嫌いのプレイヤ志向」がすべてのぼくの原点になる。この世で、自分ではなにもせず他者に言いたい放題する評論家体質の人間ほど嫌いなものはない。それは同時に、どんな形、水準のものであれ、一所懸命活動している人は認めるということにも通じる。 |
| 03/11/18 | Bill Evans──食い合わせの問題 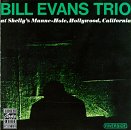 突如としてBill Evansが聴きたくなった。だがぼくはこのオシャレな白人ピアニストのCDをほとんど持っていない。いわゆる寄せ集め、コンピものはあるのだが……。 なぜかかの有名な名曲名演奏「Waltz for Debby」が聴きたくてたまらない。農作物用コンテナ三箱につっこんであるCDをひっくり返していたら運良く見つけることが出来た。正規のアルバムではない。恥ずかしいがそれは秋葉原で買った安物CDで、なにをどうしたのか「Count Basie & Bill Evans」というものだった。なんなんだろう、この組み合わせは。それでも喜び勇んで掛ける。疲れたときに甘いものが欲しくてたまらないのと同じで、やっと目的の曲にありつけてうれしい。なのに瀟洒なピアノトリオの曲が終り、喜びの余韻も醒めないうちにビッグバンドのCount Basieが流れてきて興ざめとなった。急いでとめる。たとえるなら甘鯛の刺身で日本酒を飲んでいたら、次のつまみとしてフランクフルトソーセージが出てきたようなものだ。 ビッグバンドは好きだからたくさんもっている。Count BasieはもちろんDuke Ellington、Grenn Miller等。気だるい午後に聴くグレン・ミラーなんて最高だ。 もう何十年前になるのだろう、倉本聡の書いた大竹しのぶと萩原健一主演のドラマがあった。TBSで夜の10時から。大竹しのぶがうれっこ芸能人で、そのマスコミに隠れてする恋愛、大仰にさわぎたてる週刊誌を批判するテーマで描いたものだった。当時彼女は中村晃子の恋人、服部某(後のニチカくんのお父さん。故人)を略奪愛してその渦中にいた。大竹しのぶ応援歌として倉本聡が書きおろしたものだった。彼女が今四十代後半だとすると二十二年ぐらい前のドラマとなろうか。あのころはぼくもけっこうテレビドラマを見ていたのだ。今はいっさい見ないが。 その中でグレン・ミラーの曲がテーマ曲、挿入歌として使われていて、いい雰囲気だった。上手な音楽の使いかただった。あれって倉本さんの指示なのだろうか。訊いてみたいものだ。「ムーンライトセレナーデ」が主題歌、挿入曲が「茶色の小瓶」だった。逆かな? なんて書いてたらグレン・ミラーを聴きたくなった。当時のぼくはJazzを知らない。 そんなわけで決してビッグバンドが嫌いなわけではないのだが、地下のJazz Clubで小粋なピアノトリオの「Walz for Debby」を聴きたい気持ちと、いかにもキャバレー的なライザ・ミネリが踊り出すんじゃないかって感じの派手派手賑やかなCount Basie楽団の音楽はかみ合わない。刺身とステーキのどっちがうまいかって問題じゃない。どっちもいい。でもそのときの気分で違う。時と場がある。ごっちゃで出されても困る。いったいこんな組み合わせ、誰がやったのか。センスのかけらもないごった煮である。 パソコンはありがたい。12曲の中からBill Evansのみを飛び飛びに選んで聴いたり出来る。でも毎回設定しなければならない。面倒だから分けてみるかと思う。 近年のCD-RWつきのパソコンを買ったなら誰もが一度はやるのであろう「複数の音楽CDから好きな曲だけを集めて自分だけのお気に入り音楽CDを作る」という行為をぼくはまだやったことがない。それだけ他者の曲を熱心に聞く気持ちに欠けているとも言える。アルバムとして完成されているJazzやClassicの名盤ではそんなことは不要だったからとも言える。写真や文章の保存のために焼いたことはあるが……。 サトシが最近そういう自分だけの音楽CD作りに凝ってますとメイルをくれたのはいつだったろう。彼の部屋に泊めてもらったのが2000年の2月だったから、その前になる。1999年の出来事か。たいしてパソコンを好きでもないサトシが99年に凝って、たぶん今じゃすっかり飽きて卒業したこと(推測)を、今頃うまく出来るだろうかと案じつつやるのも奇妙な気がする。まったくおれってパソコンに詳しいのか詳しくないのか。得意不得意がかなり偏ってはいるのは自覚している。 なんとか無事に分離手術に成功。假想CD-RomにBill Evansの7曲が加わった。近いうちに彼の名盤を何枚か買ってこないと。ホーンは好きだからけっこうそろっている。ギターは言うまでもない。ピアノが弱い。大好きなオスカー・ピーターソンとバド・パウエルぐらいしかない。過日書いたがギター系しか弾けないからギター系CDを中心に買っていたという迷走からやっと抜け出しつつある。 |
| 03/11/21 | 削除したCD──Remixの出来不出来 乱雑にCDをぶっこんである農作物用コンテナから出てきた一枚。もらいもの。 乱雑にCDをぶっこんである農作物用コンテナから出てきた一枚。もらいもの。タイトルにもなっている名曲「SideWinder」に「Lee Morgan」とクレジットされているから、いわゆる「名曲寄せ集めCD」なのだと思い、内容も確かめず假想CD-ROMにして聴いた。 こういう企画ってなんと言うのだろう。Remixか? どうやら原音の一部を活かしバッキングを変えたりしていじくり回したものらしい。 この手法ではクリント・イーストウッドの作ったチャーリー・パーカの映画『バード』が名高い。あの音は他者では出せないと、劇中の演奏シーンでも、パーカーのサックスの音だけは本物を使い、あとは現在のミュージシャンの音をかぶせたのである。たいへんだったろうな。 映画『クロスロード』ではロバート・ジョンソンの音をライ・クーダーが演奏したのだった。 このCDは、曲の前後に様々な効果音を入れたりして、リー・モーガンのトランペットだけ原音を使い、リズムセクションはロックにしてみたりとか、そんな試みをしているようだ。 2曲目はHorace Silverの名曲「Song for my Farther」。いきなりSEの赤ん坊の笑い声が聞こえてきた。安易と言うかあざといと言うか、誰でも思いつくいいかげんな発想だ。すこしも楽しくない。 大好きな古いJazzの名曲が新しいアレンジ、リミックスでよみがえったというより、なんか大切なものを汚されたような気がして止めた。假想CD-Romも削除する。つまらんものを時間を掛けて假想CD-Rom化してしまった。時間の無駄だ。 Jazzの普及のためにこういうチャレンジも大事なことかもしれない。これを聴いてリー・モーガンのサイドワインダーのかっこよさに気づく若者がいたならうれしい。でもこのリミックスのセンスはわるすぎる。聴くに堪えない。捨てるCD入り。 |
 -2
-2