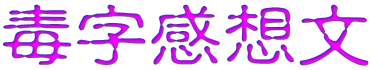  ■〈不可解な後味〉 ■〈不可解な後味〉寿司屋の親方と弟子の話である。主人公は弟子だ。こんなつまらんもののために登場人物の姓名を辞書登録してまで作る気もないので、以下「親方」と「主人公」で行く。 二人は親方が三十九、主人公が十五の時に知り合う。年齢差は二十四歳だ。田舎の中学生だった主人公は旅行に来た親方に見いだされ、東京の寿司屋の見習いとなる。中学生時代、正義感から刃傷沙汰を起こした過去のある主人公には頬に大きな切り傷がある。普段はおとなしいが、怒るとそれが浮かび上がり凄みが増す。と、ちょいと高倉健的世界のような男臭さである。こういう男同士の話は大好きだ。 それから二十四年が経つ。今現在、という設定。 主人公は今、知り合った当時の親方と同じ齢の三十九。晴れて親方から暖簾分けを許され獨立することになる。それが小説の舞台。加算すると親方は今、六十三ということになる。名人と呼ばれて名高い寿司職人だ。ここまではよかったのだが……。 ・違和感の一 オープニングは親方がうまそうにゴールデンバットを喫うところから始まる。そこからしてわからない。寿司は繊細な日本料理の中でも素手で直接飯を握るという、ある意味、どんな緻密な技術を要求される料理よりも繊細なものである。煙草呑みの握った寿司などヤニ臭くて食えたものではない。肌に染みこんだヤニ臭さは握る前にどんなに石けんで洗っても消えるものではない。それ以前に寿司職人が煙草を喫っちゃおかしいでしょう。いや田舎のひどい店ならいるかもしれないけど、この親方は銀座の名店で修行して、今では寿司好きなら誰もが知っている名高い名人であり、経済界の重鎮もこの親方の握る寿司が楽しみで通ってくるという設定だ。そんな名人がヘビースモーカーであるはずがない。 私は今まで三人ほど煙草呑みの握る寿司を食ったことがある。即座にわかった。食えたものではない。下町の安い寿司屋でもそうだ。一等地で誰もに名を知られている名人が煙草を飲むのだろうか。読んでいるだけでヤニ臭い寿司が浮かびしらけた。 伊集院静は煙草を喫うのだろう。この小説を読む限り、彼が煙草呑みをかっこいいと規定しているのは間違いない。「渋い名人職人」を設定したとき、それはゴールデンバットを喫う男だったのだ。彼がよく行く寿司屋の店主は煙草を喫うのだろう。ヤニ臭い寿司を彼はうまいと思って食べるのだろう。味音痴であることは間違いない。蓄膿症で鼻が詰まっているのかも知れない。いや冗談でも皮肉でもなく、こういうことを平気で書く人というのは、鼻が悪く匂いがわからないという人が多いのだ。銀座の一流店で修行し、今は小粋な店を出し、名人と呼ばれている寿司職人をヘビースモーカーとしただけでこの人の食に対する意識がどの程度のものであるかがわかる。それだけでもうこれは失敗作である。 ・違和感の二 親方には主人公よりひとつ年上の娘がいる。「長い間、子宝に恵まれなかった親方夫婦がやっと授かった宝物なので、何ごとにも厳しい親方も娘にだけは甘い」(原文より)という設定だ。その設定が、厳しい修業時代を送る主人公(=田舎から出てきた硬派)十六歳と、都会で甘やかされて育った不良女子高生である十七歳の親方の娘、という対比を生み出す。 その当時、親方の女房に頼まれ、主人公は娘の忘れ物を届けに行く。十六歳と十七歳。色気づいた娘は学校をサボって喫茶店にいる。不良仲間がとぐろを巻いている。そいつらが主人公に絡む。使用人なのにその態度はなんだといういちゃもん。主人公は黙って睨む。怒ると頬の傷が浮かび上がる。男はびびって黙る。それを見ていた親方の娘の女友達が硬派の主人公に惚れてしまう。なんてサイドストーリィも、チャラチャラした連中と、職人の道を真摯に生きる若者の対比となって味を持って来る。 えっ? でも……。親方と主人公が出会ったとき、親方は三十九、主人公は十五である。その主人公よりひとつ年上ということは娘の齢は十六、十六の娘を持つ三十九の親方だから父親となったのは二十三。こりゃまたずいぶんと早い結婚であり若い父親だ。その二十三の父親を「長い間、子宝に恵まれず、やっと授かった宝物なのでついつい溺愛」ってのは不自然なんじゃないの。天皇陛下とか将軍様が十五ぐらいで結婚し、二十三までお世継ぎが出来なかったらそんな言いかたをしてもいいだろうけど、それとはぜんぜん違う。それどころか寿司職人としてはずいぶんと早い結婚であり若い父親だ。それを「長い間子宝に恵まれず、やっと授かった」とはとんでもない初歩的な矛盾である。この親方も十代から銀座の寿司屋で見習いをしていたのである。そんな男が二十三で父親になったのは、見習い修行中の結婚であろう。早婚だ。それを「長い間子宝に恵まれず」は、いくらなんでも設定に無理がある。 この親方、あらゆる面において主人公の人生の師ということになっている。読めない漢字を教え、休日には名所旧跡を案内し、と主人公を一人前の男にするための指導をする。ストリップに連れて行き、トイレでの主人公の自慰を見て見ぬふりをする。一人前になるまで女には触れるなと釘を刺している。そうして田舎から出てきた十五の少年を一人前の男に育て上げた、ということになっている。でも自分は銀座の名高い店で修行してたらしいけど、二十三で父親ってことは二十二でもう仕込んでたわけだし、結婚はそれよりも早かったろうし、どう考えてもまだ店を構えた一人前ではなかったろう。矛盾してんじゃないの、言ってることとやってることが。早期結婚という矛盾はどうでもいいけど「長い間、子宝に恵まれず」のほうはどうにも看過しがたい。 ・違和感の三 この親方、戦争の思い出を語るのである。たまにポツリポツリと語る戦争の思い出話が弟子達には君子の諭しとなってためになるというお話だ。「中支戦争に行ったとき、一番先に飛び出していった集団は死なない。二番手のほうが死ぬ。敵にも準備やおそれがあるからそうなる。あれはふしぎなもんだ」と……。これは作者が実際に老人から聞いた話を元にしているのだろう、そういう含みのある言葉が語られる。 しかし、中支戦争というと六十年以上前のことだから、親方が当時二十歳で出兵したとしても現在は八十三歳以上でないと話は合わない。親方は今六十三である。これはどう解釈すればいいのか。 が、この問題解決は簡単だ。この短篇の結びは、新装開店した主人公の店に親方夫婦が現れ、合格点を出してくれるシーンである。そこで主人公はいつものように親方のゴールデンバットに火を点ける。まったく、こんなにあんな臭いゴールデンバットを頻繁に喫う寿司握りの名人などいるかよと煙草のシーンが出てくるたびに思うのだが、それはともかく、ゴールデンバットという古いタバコを喫うのであるから、このことからこれはだいぶ前の時代を舞台にした小説なのだろうと解釈できる。作者もそれを計算しているのだろう。とりあえず戦争に行った年齢を二十歳にして時間をずらし、これは昭和四十年代末か五十年代初期の話、今は親方は八十五ぐらい、主人公は六十一、二十数年前の世界、そう時間軸をずらせは、この点に関しては合点が行くのである。 だがそのことは断ってない。まあ断ってなくてもゴールデンバットから時代を読むのが読者の勤めだとしても、文章からぜんぜん昭和五十年代という趣は伝わってこない。雰囲気は今そのものなのである。この小説を読んだ読者は、普通の場合、ゴールデンバットに違和感を持ちつつも、今の物語として読むだろう。 ・違和感の四 主人公に兄弟子がいる。主人公よりは腕が落ちるが、人なつっこく別の意味で親方にかわいがられているという設定だ。この兄貴分が親方から干瓢の煮直しを命じられる。「四十も半ばになって、なんで今更干瓢の」と彼は嘆く。兄弟子は甘い物が好きだ。店に来る前に大福を買ってきて厨房に置いてある。それを時々盗み食いする。そのことで味覚が狂ってしまい干瓢の味つけを間違えたのだ。名人と呼ばれる親方は一発でその狂いに気づいた。兄弟子はそれに気づかない。主人公は味を見てみる。微妙に狂っている。それとなく兄弟子に甘いものは止めたほうがいいですよと注意する。 というようなエピソードで、いかに親方が名人であるか、それに気づかない兄弟子の鈍さ、親方同様すぐにそれを見抜く主人公の舌の確かさ、厳選された味を保つということが名店において、いかに日常の節制から生まれるか、それらを作者は語りたいのだろうが、もともとが煙草呑みの寿司握りじゃあ聞く気にもなれないのである。そんなに微妙な味を云々するのならテメーがまず煙草を止めろよと親方に言いたくなる。 以上の四つをなんとも奇妙に感じ、どっちらけになってしまった短篇だった。どんなに取り繕おうとも、父と娘の年齢等、ごまかしようがないだろう。 では何故にこんなものが出来てしまったかと考えると、「名人と呼ばれる寿司職人、彼に見いだされ、長い厳しい修行の後、見事に名人を襲名できるほどの腕のいい職人となった主人公。師弟愛。寿司職人の男っぽい寡黙な世界。主人公がやっと見つけた、母の面影を感じる十四歳年上の女。それとの結婚に反対する親方。最後には黙ってそれを許してくれて大団円」とかまあプロットとコンセプトはわかる。 それを考えついた作者は、この短篇を一気に書き上げたのだろう。その中に田舎者の主人公の苛烈な気性と硬派ぶりをアピールするために、不良っぽい親方のひとり娘を登場させたり、古い時代の頑固一徹の職人像を明瞭するために、川面を見ながらゴールデンバットを喫わせたり、味の世界をかいま見せるために干瓢と大福の話を出したりしたのだ。 筆が遅くて有名な人だから、たぶん締め切りぎりぎりに一気に書き上げ、編集者は一読して年齢の矛盾などに気づいたろうが、それを直すと物語の構成からして直さねばならないので目を瞑って見切り発車をしたと思われる。これほどあちこちに破綻の見えるヘンテコな小説もそうはない。プロットとコンセプトはよかったがディテールはめちゃくちゃという典型的な駄作である。将来短篇集として編まれるときには大幅に加筆修正されてくるはずである。でなきゃ世には出せない。どこがどうなってくるのか、意地悪な気分で『オール読物』を取っておこうと思う。 さて、ではこの小説の致命的な矛盾を解決するにはどうすればいいかと考えてみる。 まず娘は、「親方の齢の離れた妹」とするのがいいだろう。二十三歳離れた末の妹である。昔ならこんな例はいくらでもあった。彼女が生まれると間もなく母は死んだ。この母の死に長兄である親方が関わっている。母を死に追いやった責任から末の妹の面倒を見ねばならない責任感が生まれる。親方は末の妹を我が子として育てた。差別しないよう、自分たちの子供は作らなかった。母親を死なせてしまった贖罪意識から、母の顔すら知らない末の妹を過剰にかわいがる。娘には甘い。この設定でいいだろう。 タバコのシーンは削除した方がいい。男の渋さを出すのにそんな安っぽい小道具はいらない。これでなんとかまとまった。 てなことを私が考えていてもしょうがないのだが(笑)。 世の中には熱烈な伊集院静ファンも多いらしい。そういう人にぜひとも私のこの感想文がどう間違っているか指摘してもらいたいものだ。わたしには「やや寒し」どころか、凍えるほどお寒い小説だった。 (02/10/4 am7:15 ムンラ山菜酒店) 【附記】 中国旅行の際に発売されたばかりの「オール読物」を持っていって読んだときの感想。 |