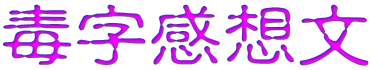  「笑うアジア」下川祐治他 「笑うアジア」下川祐治他(『作業日誌』より転載) (02/4/22) 一読して愕然とした。ぜんぜん楽しめない。笑えないどころか不愉快になって途中で放り投げてしまった。スキャンまでして絵を入れたのは次のゴミ収集日に間違いなく捨てるからである。やはりこういうものはタイでみんながよくやっているように、10バーツ程度でウイークエンドマーケットで買ってきたり、互いに持ち本を交換して読むぐらいがよく、新刊で買ってくるものではないと感じた。 しかしほんの十数年前、ぼくがこの種の本をむさぼるように読んでいたのも確かなのだ。家で読んだのはもちろん、成田空港ではこんなのばかり何冊も買いこんで、飛行機の中でも楽しみに読んでいた。時にはページをめくる手が早すぎ、出発前の空港で読み終えてしまうことさえあった。それはきっとぼくばかりではなく、アジアに惹かれたあのころの旅の初心者はみんなそうだったろうし、そして今も、これからハマる人は、同じ事を繰り返しているのだろう。 当時むさぼるようにして読んでいたこれらの本を、今では途中でうんざりして放り投げてしまうようになったのは、なぜなのだろう。まず、ぼくがアジアに旅慣れしたことがある。このことがいちばん大きな要素となるのだろう。この本に書いてあることを驚くことなく読めるほどぼくもアジアにスれてしまっている。ぼくがこの本を楽しめなかったと言ったら、だれもがそういう解釈をするに違いない。そして、それで一件落着となる。 たとえばこの本の一章に、尻を手で洗うトイレ初体験の話が出てくる。ぼくは最初の時から素直にとけ込めたし、そんなのはあたりまえだと思っているから、そのことを「たいへんだ、紙がない、さてどうしよう。ぼくは青ざめた」と持って回った言いかたをして大仰に騒ぎ立てる筆者と一緒に楽しむことは出来ない。 そのことを、ぼくが旅慣れしたからと理由つけすることは出来る。でも違うんだなあ。「笑うアジア」と題し、文章で笑いを取ろうとするなら、最低限の文章のノウハウを身につけていなければならない。ところがここに書いているような青年は、トイレに紙がない、お尻の穴を自分の手で洗わなければならない、たいへんだたいへんだと、ただそれだけの事実で笑いがとれるものと勘違いしている。 コントで言うなら、舞台にバナナの皮があり、滑って転べば、ただそれだけで観客は笑い転げると思いこんでしまっているのと同じだ。言うまでもなく、そこで必要なのは転ぶ技術だ。なのにこれらのライターは、自分で転び、観客が笑う前に、真っ先に自分が、まいっちゃったよ転んじゃったよと笑い転げている。観客としては、しらけ、引いてしまう。なのに本人は涙を流して笑い転げていて、観客の気持ちに気づかない。そんな本である。 だけど、たとえば、冒頭にある一章などは、外国で知り合った男を、日本人の獨身三十女が30万円ほどかけて日本に呼び寄せ、そこから始まる異文化のドタバタを、おもしろおかしく(と当人は思っているのだろう)書いた話なのであるが、ぼくからすると、その男を四畳半一間と三畳のキッチンの自分の部屋に泊め、当然のごとく迫ってきた男を外国ではそうだったけど今はもう恋人同士じゃないんだからやめましょうねと説得し、おとなしく寝かしつけた、そうしてそれから奇妙な同居生活が始まった、なんて話を読んでいるだけで、このオンナどっか壊れてるぞと思ってしまい、笑うどころの話ではないのである。 その後その外人(南洋系のゴツい男)が日本の習慣を知らずいくつかの問題を起こし、その対処に翻弄される書き手の女性は、へとへとになってしまった、お金ももうない、まったくとんでもない男を呼んじまったってな感じで笑いを取ろうとするのだが、ぼくからすると日本人バカ女が気まぐれで発展途上国の男性をもてあそんでいるようで、あちらこそいい迷惑だろうと思えてしまい、落ち込んでさえくる。 なんか、オカシイわ、この本は。ぼくは前々からパックパッカーが嫌いだと公言しているけど、そのバックパッカーの軽薄さが凝縮されたような一冊だ。新刊で買った本だからもったいなくて、捨てるまえに通読しようと思ったが、そんなせっかく注文したのだからとまずい料理を無理矢理残さず食べようとするようなことはやめることにした。 端的に言えばそれはトイレである。水洗トイレ、トイレットペーバー、時にはウォシュレットのような日本の日常から、手でお尻の穴を洗う体験をしたことを大げさに騒ぎ立てているわけだけれど、そのことに、アンドレ・ザ・ジャイアントを取り囲み、バケモノだバケモノだと騒ぎ立て、バケモノの意味を知ったアンドレが日本人を大嫌いになってしまったという日本人の無神経さに通じる不快さを感じる。西洋人が日本に来て、日本の家は紙と木で出来ている、ぼくらみたいに石じゃない、これじゃすぐつぶれちゃうな、燃えちゃうなと笑い転げたら不快になる気持ちをもっていれば、異国のトイレでこんな大騒ぎは出来るはずがない。 ぼくは今まで何十回も自分のことを「旅人気質がない」と、旅をするのに適した資質に欠けているタイプと書いているけれど、こういう無神経さがそれなら、そんなものはいらないし、そうでなく、人それぞれの生活を偏見なく観ることが有効な気質とするなら、こんな人たちよりは遙かにそれを持っていることになる。 こんなくだらないもののことを真剣に論じていてもしょうがない。ぼくが今興味あるのは、十数年前、まだアジアのこれらを知らないときなら、ぼくはこの本を興味深く読んだのだろうかという假定である。 たぶん、間違いなく、いや確実に、ぼくは当時でも、今と同じ感覚で拒んだと思う。なぜなら、ここにあるクササと、それに対するぼくの反発は、決して未体験既体験という単純なものではなく、人生観、民族観、世界観に通じるものだと思うからである。そして、ここにあるような軽いノリの軽薄体文章であっても、たとえばクーロン黒沢さんの文章などはすなおに楽しめたのだから、やはりいくつもの意味で、これが全体的に水準に達していない素人本であることは確かだろう。 (後日記入。やはり捨てる前にもったいないと通読したら、岡崎ダイゴという人の文章は水準以上で楽しめた。) (02/4/28)  ←捨てた本① ←捨てた本①基本はすでに書いたように、「日本の今を前提として、他国の状況を笑おうとする、今の若者的な底の浅さに対する反発」である。そのことを考えているうちに、これは「差別したいけど、今の日本では出来ないから、それを海外でやっているのではないか」と思えてきた。 私は性悪説を採っている。赤ん坊がわがままと身勝手の象徴であるように、本来の人間とは缺陥だらけの残酷な性質を持っていて、それが社会生活の中でしつけられてゆくものだと。 子供は、残酷である。汚い身なりの乞食がいたら囃し立てる。いじめる。びっこで歩くのがヘンな格好の人がいたら、からかう。それが根本の性質だ。それをおとながいさめる。それは人としてよくないことだと教える。そうして覚える。それを年下に伝えてゆく。 ボロな服がある。つぎが当ててある。それが破れ、つぎの中にさらにつぎをあてたようになっている。私が子供の頃、貧しい農家の子供はそんな服を着ていた。青っぱなを垂らしていた。それを服の袖で拭くものだから、袖は鼻水が固まり、てかてかと光っていた。勉強も出来ない。みんなでからかいいじめる。先生に叱られる。心ある大人に、自分たちがいかにひどいことをしているか諭される。謝りに行く。なかよしになる。そんなことをして学んでゆく。 いま日本には、そこまで貧しい人はいない。乞食もいないことになっている。それでもそういう存在を囃し立て、からかい、いじめるのが人間の本質なら、代償行為を探すようになる。若者がホウムレスを襲う。鴨や鳩にボウガンを撃つ。犬猫の手足を切ったりする。これらは見かけだけはきれいで平等な社会になった今の日本から噴出した当然の吹き出物であろう。 外国のゴツい男を、日本人の獨身三十女が、金をかけて日本に呼ぶ。彼女は男を〃野人〃と呼び、文化の異なる日本で彼の巻き起こす騒動をおもしろおかしく(私にはすこしもおもしろくないが)書く。笑えない。 むかし、智慧遅れで、よだれを垂らし、体の大きい、力持ちの男、のようなタイプが、田舎にはいた。亭主を早く亡くした後家が、こういう青年を家に引っ張り込んでイタズラし……、なんて話がよくあった。 私がこの文章から感じるのは、それと同じような不道徳さである。費用は30万だったそうだ。小銭のある日本人バカ女が、経済的に下の外国人男をもてあそんだと、それしか感じない。 金持ちの子供が貧乏人の家に遊びに行く。掘っ立て小屋のような家の一間に家族七人で住んでいた。便所は裏にただ穴を掘っただけのものだった。いらっしゃいませと縁の欠けた茶碗で水を出された。金持ちの子供は、次の日、学校で、その驚きを、同じ金持ちの子供たちにしゃべる。貧乏人の子供は赤くなってうつむく。ぽくが子供の頃の日本の現実だ。 今の日本にそれほどの貧乏人はすくない。それを囃し立てたりすること禁じられている。しかしそれをやりたがるのは子供の本能だ。だったらどうする。外国でやる。 尻を手で洗うタイプのトイレをとんでもない大事と騒ぎ立てる文章などは、これだろう。 アフリカの野生動物の中を、金網で防護されたバスに乗って見学するツァーがある。私はこの本に登場する旅行ライターたちに、それと同じ感覚を受けた。金網で防御されたバスではなく、体ひとつで歩いていると彼らは言うかもしれない。でも懐に入れた何十万円かのトラベラーズチェックと日本のパスポートは、同じようなものだろう。たまにバスは、ライオンを始めとする動物に襲われ、ひっくり返され、人間が食われてしまったりすることがある。私は、このバックパッカーと呼ばれる人たちのバスがひっくり返り、そうなることを、いつしか願っていた。 バックパッカー、およびそれに類する旅人は、日本で自分の思うほどの評価が得られず、それを探しに異国に出たというのが私の意見である。だから、常に日本を意識し、文化、経済、すべてを、日本と、自分と比べて、より上である自分に満足する。それは、日本でしようにも出来なかったことだ。 「彼らの月収は一万円。日本でなら一日のアルバイトで稼げる金だ。貧しい。気の毒だ。涙が出た。だが彼らの目は美しく輝いている。大切な物を無くしたのはぼくたちのほうかも」 くだらん。よくぞこんなことがかけるものだ。 貧しくなんかない。貧しいのは、そういう比較でしか物事を考えられない彼自身だ。そのことのほうがよほど悲しくて涙が出る。 「小学校しか行けず、小さな体で働き始める。かわいそうに。これもみな貧しさが悪い」 貧しいのは、親の金で三流大学に行き、なにをしたらいいか解らずに海外旅行に出て、他人のことをそんなふうに評価して自己満足しているあんたのほうだ。「小学校しか行けず、小さな体で働く」人を哀れむより、大学にまで行きながらその程度の発想しかできない自分を恥じろ。 パックパッカーが嫌いだとは前々から公言してきた。その理由は、地に足がついてないからで、私は日本で一所懸命に(それこそこの言葉の語義である〃一所〃だね)に働く若者のほうがずっと美しいとしてきた。私の嫌いなバックパッカー的感覚が牛詰めされたものとして、この本を反面教師としよう。捨てるのはちょっと早すぎたか(笑)。 下川祐治という人は、初期の本は楽しく読ませてもらったし、彼自身もこういう形で自分が権威になってしまうとは、望んでもいなかったろうが、こんな本を編著するようになっては終りである。旅ジャンキーがクスリ自慢をしているようなひどい本だ。  ←捨てた本② ←捨てた本② |