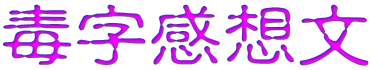 捨てた本 捨てた本

 ──高野悦子 ──高野悦子
 引っ越しのために多くの本を捨てた。中心はオオエとか、オダマコトのような学生時代にファッションとして買ったもの、野坂五木イノウエ等の今後読み返すことのない対談や小説等である。 引っ越しのために多くの本を捨てた。中心はオオエとか、オダマコトのような学生時代にファッションとして買ったもの、野坂五木イノウエ等の今後読み返すことのない対談や小説等である。
大がかりな本捨ては三十そこそこのころから二度目になる。悔やまれるのはそのときに今回のオオエ等を捨てられなかったことだ。当時それなりに結論は出ていた。読んでもいなかった。おもしろくないし思想的に共鳴できないと結論が出ていた。なら真っ先に捨てねばならないのだが、なんとなくそういうリッパな本を捨てるのはよくないことではないか、という迷いがあった。好きではないが一目置いていたと言えばいいのか。自分に自信がなかったのである。彼らと同調できないし嫌いなのだけれど、思想としてそれを説明できるだけのものが感覚的にしかまだ固まっていなかった。
今回は迷わず真っ先に捨てた。二十年たっていくらか賢くなっている。
すべてハードカヴァーの初版本だから好事家には垂涎の的でもあろう。燃えるゴミとして捨てた。そういう捨てた本のことを書こうと思ったら、代表的な一冊として、今回ではなく前回捨てた本の一冊を思い出した。捨てる本についてそれを例に書こう。言いたいのは、この本一冊のことではない。「この本のような本」についてになる。
 この「二十歳の原点」というのは、立命館大学で学生運動をしていて自殺した二十歳の女子学生の日記を起こした本である。これは迷わず前回の本捨ての時に捨てていた。駄本である。よって画像を拾ってくる気もない。 この「二十歳の原点」というのは、立命館大学で学生運動をしていて自殺した二十歳の女子学生の日記を起こした本である。これは迷わず前回の本捨ての時に捨てていた。駄本である。よって画像を拾ってくる気もない。
が、なぜか「新潮文庫の100冊-CD-ROM版」に入っていて、雲南で本に飢えてこのCDをひろげるたびに、タイトルを見かけ思い出させられることが多かった。そうでなかったらとっくに忘れている一冊である。それと、後に岩波ホールの支配人が同姓同名と知り、彼女の名を見かけるたびにもこの本のことを思い出させられた。
まったくこの「新潮文庫の100冊」の選び方には首をかしげる。どう考えても新潮文庫のベストではない。それどころかCDに百冊も入れるのだからいいものを入れたらもったいないとケチっているのが見え見えだ。それでもたった一枚のCDを持っていれば(実際にはハードディスクに入れてあるのでもってさえいないが)異国で活字に飢えたぎりぎりのとき助かるので重宝している。山本周五郎や井伏鱒二の文に触れられるだけでほっとする。その意味では価値のあるCDだ。
 この本のことを思うと、時が流れても第一印象は変らないものだと了見する。当時青春の必読の書として話題になったのでリアルタイムで読んだが感想は今も昔もかわらない。つまらん本だと思った。というか、あえて本にするほどのものではない。女子大生のノートに綴ったプライベートな日記でしかない。彼女だって本にしようと思って書いていたのではない。編集者がすばらしい文章だと目をつけたわけでもない。本になったいちばんの原因は、自殺した娘のことを世に遺したいと願った父親の熱意だったろう。 この本のことを思うと、時が流れても第一印象は変らないものだと了見する。当時青春の必読の書として話題になったのでリアルタイムで読んだが感想は今も昔もかわらない。つまらん本だと思った。というか、あえて本にするほどのものではない。女子大生のノートに綴ったプライベートな日記でしかない。彼女だって本にしようと思って書いていたのではない。編集者がすばらしい文章だと目をつけたわけでもない。本になったいちばんの原因は、自殺した娘のことを世に遺したいと願った父親の熱意だったろう。
思うにこういうのは、時代への思いこみなのだ。きまじめな娘が大学に入り学生運動に熱中する。迷いの末に自殺する。遺されたものはなんともたまらん気持ちで、その日記を抜粋して本にする。多少関わり(現実的にも幻想的にも)があったものは自分の痛みとして読む。関わりのないものは、関わらなかった後ろめたさで覗き読みする。マスコミは大きく取り上げる。そういう時代だった。読みかたはどうであれ、問題はそれに耐えうるだけの中身を本が持っているかだ。
私が読んだのはそれこそ二十歳の頃であり、この人はすこし年上だったと記憶しているが、一読してつまらん本だと思った。遺族(父)がだいぶいじった(露骨な性的表現等を削除した)らしい。たしかに空しいことの比喩として、「空に屹立した男根、空虚なままの女陰」ノヨウナ表現があったことを記憶しているから、原文には著者の経験した男性体験が父からは見るに忍びない形で書かれていたのかもしれない。だが生のままだとしても、私にはそれこそ他人の日記を覗き読みするような後ろめたい感想しかなく、それは覗いてもすこしも楽しいものではなかった。ひとことで言ってしまえば、溺愛していた娘を失った父親が執念で本にした、とそれだけのことだろう。
 一読して私がなによりおどろいたのは、この娘の自信過剰だった。自分を美しいと意識し、並より美しいことになんの意味があろうかというような問いかけをたびたびしている。頭脳のほうも立命館に入学した自分に誇りを持っているようだった。自分は容姿的にも頭脳的にも経済的にもエリートである。だが世の中にはそうではない人が多い。彼らを解放するために、自分は恵まれたその立場に甘んじてはならないのだと自戒しているのだが、彼女をそれほどのものと評価していないこちらとしては、自信過剰自意識過剰の若い娘のたわごととしか受け取れなかった。そういう性格だから自殺に走ったのだろうが……。 一読して私がなによりおどろいたのは、この娘の自信過剰だった。自分を美しいと意識し、並より美しいことになんの意味があろうかというような問いかけをたびたびしている。頭脳のほうも立命館に入学した自分に誇りを持っているようだった。自分は容姿的にも頭脳的にも経済的にもエリートである。だが世の中にはそうではない人が多い。彼らを解放するために、自分は恵まれたその立場に甘んじてはならないのだと自戒しているのだが、彼女をそれほどのものと評価していないこちらとしては、自信過剰自意識過剰の若い娘のたわごととしか受け取れなかった。そういう性格だから自殺に走ったのだろうが……。
それこそ「覗き見」の視点からなら、二十歳の女子大生のサンプルとして冷笑嘲笑も出来たかもしれない。当時も今もそんなものに興味がない私には、はなはだ鼻白んでしまう一冊でしかなかった。といって、これまた時代的にそう口には出来なかった。
こんなものが本になり、今も文庫で出されるだけの価値があるとは私にはどうしても思えない。その考えは初めて読んだ当初から今に至るまでかわっていない。視点を変えるなら、あまりに未熟なそういう悩みだからこそ永遠の青春として後世に残す価値を見いだせる、と言えるのかもしれないが……。だけど私の知る限り青春の悩みってのはもっとみんな謙虚だった。
 ただ、こういうものが記録として存在すること、若いときにこういうものを手にすることはそれなりに必要なのだろう。私のように一読して投げてしまったとしても、同じく二十歳の人たちが、「読まねば」と意識することは大切なのかもしれない。また、読みもせずくだらんと否定してもいけないのだろう。この本に感動するのはどんな人だろう。著者と同じく自信過剰自意識過剰の人か。 ただ、こういうものが記録として存在すること、若いときにこういうものを手にすることはそれなりに必要なのだろう。私のように一読して投げてしまったとしても、同じく二十歳の人たちが、「読まねば」と意識することは大切なのかもしれない。また、読みもせずくだらんと否定してもいけないのだろう。この本に感動するのはどんな人だろう。著者と同じく自信過剰自意識過剰の人か。
この本がこちらの胸に共鳴して感情をざわつかせるものでないことは、すくなくとも私には、真実である。キャンパスで知り合っても親しくはなれる人ではなかった。藤原伊織の「テロリストのパラソル」を、「全共闘世代の残映、センチメンタリズム」なんて評する言いかたがある。この駄本を青春の記念碑のように褒め称えたのも時代と世代であったろう。
(03/6/10)


2ちゃんねるの「一般書籍」の項、「泣けた小説」というスレッドを読んでいたら、何度もこの「二十歳の原点」が出てくるので驚いた。書き込んでいるのは若い人たちのようだ。とすると、「新潮文庫の100冊」に入っているぐらいだから今もこの本は「青春の必読書」とされていて、今の若者(といっても読書好きに限られるが)にもそれだけの感動を与えているらしい。こんがらがった。
間違ってもこの本を読み返したり買ったりすることはないと思っていたが、そこまで評価されているのなら、CD-ROM「『新潮文庫の100冊』に納められているから読み返すことは出来る。読み返してみることにした。
「『二十歳の原点』を二十歳のときに読んでつまらないと思った」は私の三十年前の真実である。それが変るとは思えないのだが、三十年ぶりに読み返したら当時はなにも感じなかった部分に共鳴し涙が止まらなかった、なんてことになったら、それはそれで正直に告白しようと思う。
今の時点での予測では、その若者たちがやっている「泣けた小説」でも、誰かが「涙が止まらなかった」とやっている作品に対し、「おれはあれを読んだら引いてしまって泣くどころではなかった」との書き込みもある。どうにも読み返した私が感動する、というパターンは想像しにくいのだが、それでもそういう評価の分かれる様々な作品の中で、この作品に対する否定的な評価はない。学生運動を知らない連中には否定できないとも言えるが。読み返したらまた【附記】しよう。(04/10/19)

|