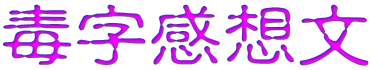

 「江戸前の男──春風亭柳朝」 「江戸前の男──春風亭柳朝」
 むかしを思う資料としての一冊 むかしを思う資料としての一冊
吉川潮という人の文章はつまらない。この本も物語として読んだらすこしもおもしろくない。巻末に資料一覧があるが、そこから抜き出してきたものを並べ立てただけである。また私はこの落語家にも興味はない。子供のころテレビでよく見た人だったが好きではなかった。
ならなぜ読んだかというと、まず一時は志ん朝、談志、円楽とともに若手四天王と呼ばれた人だから、チラっと中身を見たら当然のごとく彼らのこと、当時のことが書いてあったからである。それらを読みたかった。
それと、ちょうど「こぶ平の正藏襲名」が話題だった。柳朝の師匠は蝶花楼馬楽、八代目林家正藏である。一代限りで林家から名跡を借りた後の彦六だ。そのいきさつも書いてあるだろう。そこが読みたい。また弟子の小朝の入門時のこと等が書いてあるに違いない。いわば物語の周囲を情報として得ようと思った。
結果としてそれは成功でありその点では読んで良かったと素直に思っている。林家喜久藏のことが書いてあったのも思わぬひろいものであった。
発刊は1996年。新潮社。
---------------
しかし、といきなり批判的な点から書き出すのも気が引けるが、いやそういうことを書く「毒字感想文」なのだと尻を叩いて書いてしまおう、この本の狙いはなんだったろう。演藝評論家、テレビ評論家として食っている吉川がことさら柳朝のファンだったとは思わない。もしもそうだったならこの本からはその想いが迸ってこなければならない。そんなものはない。前記したように資料本から得たものを順番を間違えないように並べてあるだけだ。小説的味つけは冒頭に死の近い病室を持ってきてのプレイバック形式をとったぐらいだ。登場人物もまったく描けていない。無味乾燥な本である。私としては資料としてあげてある小朝や喜久藏の本をあらためて読みたいと思わないので、それらからエッセンスだけを吸い取ったこの本がちょうどいい。欲しいだけの知識をもらって感謝するけれど。
これでもしも彼が柳朝の大ファンだったなら、今度は熱さの伝わってこない抜け殻のようなこの文章を批判されることになる。熱さの伝わる文章を書ける人ではないが、大ファンだったとしたらこの文はひどい。そうではないと解釈した方がまだ救われるだろう。だったらなぜ書いたか。
吉川の狙いも「時代」だったのだろう。志ん朝、談志、円楽を描くにはそれぞれ垣根が高い。自分のことばをもっている。いちばん近しい談志などたっぷりともう当事者でなければ書けない貴重なことを書いている。書きまくっている。近寄れない(立川流顧問だが)。
かといって志ん朝、円楽も……。だがあの時代は描いてみたい。この「時代」を描く突破口として、吉川は当時から三人ほどの人気もなく、早死にした柳朝を選んだのだ。「切り口」として。そう解釈すれば柳朝に関してすこしも熱さが伝わってこないことも納得できる。
それは方法論として正解だろう。この本を手にする多くの人も、熱心な柳朝ファン以外は、みな当時のそれを知りたいと願う演藝ファンのはずだ。だからこの本には、私のようなのが当時のことを思い出したり、当時を知らない人が勉強するのにはそこそこの価値があるが、春風亭柳朝という落語家を知らない人がこれを読んで彼の熱心なファンになる、というような効果はない。むしろ彼の熱心なファンだったなら柳朝も女房も描けていないこの本の出来の悪さに怒るかもしれない。柳朝の友人に叮嚀に取材した過程は見て取れるが。
と、総論はさておき、私はこの本から得たいと思っていた情報をずいぶんともらった。たいそう感謝している。それらを列記したい。私にとってこの本はそれ以上でも以下でもない。
---------------
●正藏襲名事件
あらかたは判っていたが数字的な細かいことまでは知らなかった。メモしておこう。
蝶花楼馬楽が四代目小さんの一門になったのが大正十二年。五代目小さんになる弟弟子、当時小三治が入門したのが昭和八年である。十一年後輩になる。そのあいだには鈴々舎馬風もいる。それが馬風や自分を通り越して五代目小さんになるというのだから馬楽が怒ったのも当然だった。
これを仕掛けたのは「次期会長間違いなしの実力者」文楽だが、馬楽の怒りの激しさに収拾がつかなくなり、文楽の師匠、高齢の大御所、柳亭左楽まで登場しての馬楽宥め作戦となる。そうして林家正藏襲名という案が出る。
これを「柳亭一門の自分がなんで林家の名を」と拒んだ馬楽の感覚は正当である。
私がこの件で強く思ったのは「林家の悲劇」である。
私もなにも知らないときは「七代目は三平の父親のおちゃらか藝の正藏。その名跡を借りたのが、一代限りの彦六正藏。名人彦六。この人が正藏の名を高めた。約束を守ってそれを生きているうちに返済した潔さ」であった。いわば「八代目贔屓」である。それはちゃらちゃらした林家三平一門への反発意識だったのかも知れない。
三平本人はともかく、来るもの拒まずで誰でも弟子にしていたものだから、どんな番組にでも三平の弟子が顔を出していて、それでいて誰もまともな藝はもっていない三平一門の有象無象は目障りだった。大嫌いだった。
私は林家一門嫌いの彦六礼賛派だったことになる。
しかし「笑伝 林家三平」(神津友好)を読んでからすこし考えが変った。これはこれが好著だったとかそういう理由ではない。単に林家嫌いで感情的に判断していたのが、数字的に見ると林家にとってひどい話だと思うようになったのだ。
正藏が亡くなったのが前年の十月。翌年の五月に、前記の連中の仲裁により馬楽は八代目正藏襲名興行をしているのである。それは五代目小さん襲名を四代目の命日である九月三十日にさせるために急がせたのであろう。
とすると、この左楽まで出てきて大もめしているころは年明けぐらいか。正藏未亡人は一族の大切な名跡であり亡き亭主の名を四十九日が明けてすぐ(もしかしたら明けないうちに)に、左楽や席亭から、まったく縁もゆかりもない噺家にもめ事を収めるために名跡を貸してくれと頼まれたことになる。しかも跡継ぎの三平はまだ売れていない二つ目。三平の嫁と一緒に内職で食いつなぐ赤貧の日々だった。
落語界の実力者たちからそういう無理強いをされ、神津の本にあるように、力のない我が身を呪い悔し泣きしたのは事実であろう。大黒柱を失った落ち目の悔しさである。それもまた三平のあの爆発的なエネルギーにつながっているのかも知れない。
これはこの本ではなく文楽関係の本で読んだのだが、文楽がこの件に関して、師匠左楽に強引なことをして問題を起こしてすまないと詫びたそうである。すると左楽は「なにいってんだ、おまえを文楽にするときだってどれほどもめたことか」と呵々大笑したそうだ。
文楽が師匠左楽の引きで八代目桂文楽を名乗ったのが二十八の時である。名人文楽ということですっかり忘れられているが襲名の時はそうだったらしい。結局落語界には「よくあること」なのであろう。始まりはどうでもいいわけだ。のちにそれを名に恥じないものに仕上げるかどうかである。
---------------
●昭和の年譜
昭和三十一年、志ん生が「お直し」で藝術祭賞受賞。落語協会の会長就任。次男強次が朝太の名で入門する。後の志ん朝。
三十二年。三月に小金馬、四月に歌奴、十月に三平が真打ち。
藝術協会は、春風亭柳昇、柳好、桂伸治、三笑亭夢楽、桂小南の六人同時真打ち昇進。
なつかしい名前ばかりだ。当時も今も落語が巧くない小金馬が早く出世できたのはNHKの「お笑い三人組」に出ていたからだろう。全国的に名を売ったのが早く出世するのは今もむかしも変りない。私は圓歌がきらいだけれど(それは間接的に接するものからの判断だが間違いないと確信している)歌奴当時の彼が自作の新作落語で人気を得、実力でのしあがった人であることはすなおに認める。人気者だった。「授業中」を何度聞いたことだろう。
三十四年。一月にNHK教育テレビ開局、二月に日本教育テレビ(NET→テレ朝)、三月にフジテレビ開局。
フジテレビの開局の方がNETよりすこし先だと思っていた。事実は逆。勉強になった。
フジテレビが「お笑いタッグマッチ」という演藝番組を始める。レギュラは柳昇、米丸、伸治、柳好、小円馬、夢楽、小せん。
私の記憶には、小学生時代から中学生時代にかけて、この人たちのことが強烈に残っている。柳昇、米丸、伸治は落語もだいぶ聞いているからいいとして、柳好、小せんのように今でも似顔絵を描けるぐらい馴染んだ人だが落語の演目ではなにも覚えていない。それは当時のそれらの番組が今で言うヴァラエティ番組のようなものであり、テレビへの露出度は高くてもまともな噺はしていないからだろう。
そうして即興でやる部分がまったくおもしろくなかった。私は落語家に失望する。彼らをお笑いのプロだと崇めていたからだ。でも彼らはある種の古くさい落語家であって、稽古して身につけたものを忠実に再現する藝は巧くても、その場の笑いに当意即妙に対応するだけの能力は有していなかった。
そこに抜群の反応力を誇り、それが出来る人として円鏡が売り出してきて人気者になる。ただし彼はあくまでもそれまでの落語家と比してあたらしい感覚だったというだけで、私の望んでいるものではなかった。
当時談志も蝶ネクタイ姿で登場して漫談を演ったりしていた。だが彼の漫談は、アメリカのボードビリアンを意識したものであり、ハリウッド映画やミュージカルを題材にしたりして、「こんなオシャレなネタはおまえらにゃちょっとわからねえかな」が鼻につき、むしろイヤミな嫌われ者であった。私の願うだけの感覚の藝人は、ビートたけしの登場まで待たねばならなかった。
談志はたけしに対し、たけしのやっていることは全部おれがやってきたこと、たけしなんておれをちょいとソフトにしただけだ、と言う。その通りかも知れない。でも背伸びし突っ張り通して嫌われていた談志と、年寄りの悪口を言いつつも年寄りにも好かれてしまったたけしを比べると、その差は大きい。それが時代的なものか個人的なものかはともかく。
---------------
●柳朝の真打ち辞退
昭和三十五年に柳朝(当時は照藏)は真打ちに昇進することになる。ところが藝を認めていない大嫌いな正蝶と一緒の昇進だというのでこれを拒む。正蝶は年上で兄弟子に当たる。だがよそからの預かり弟子だった。彦六正藏の一番弟子は自分だという誇りがある。
落語界の序列は早く真打ちに昇進した順である。一生それを引きずる。それを敢えて遅くなってもいいからあいつと一緒の昇進はイヤだと拒んだのである。とんでもないひねくれ者だ。しかし私はそんな柳朝に親近感をだいた。
私が「オグリキャップ写真集」というものを出すとき、「写真・久保義輝 文・結城恵助」と表紙に同じ大きさの大きな活字でデザインされていた。『優駿』でタッグを組んでいた二人の作品集として出る予定だった。もともと馬のオーナーが二人を指名してきて始まった話である。
最終稿があがったとき、私はまったく知らないあいだにKという女編輯者に文章をかってにいじられていたことを知る。それで、あれはもうおれの文ではないと、印刷に入る直前に表紙から私の名前を削ってもらった。デザイナはこういう共著の場合、おれの名前を上にしろ、もっと大きくしろとの我を張る内輪もめにはさんざん悩まされてきたが、名前を削除してくれというのは初めてだったので戸惑った。本が出てからそれを知った久保さんにもなんてことをしたんだ、なんでおれに相談しなかったんだと嘆かれる。(相談していてはもう間に合わなかったのだが。)
私のやったことは愚かである。でも世の中には私と同じようなことをする柳朝のような人もいるのだと知って心強かった。
---------------
●喜久藏のこと
昭和三十六年一月十六日。三代目桂三木助死去。
師匠の死により弟子は他の師匠の預かり弟子になる。三木助には五人の弟子がいた。世話人の文楽にどこに行きたいかと問われた前座の喜久男は「正藏師匠のところです」と応える。
預かりが許可された。正藏は喜久男のままで行くかと問う。正藏の弟子になったから藏の字をとって喜久藏に替えるかと言われる。そうして前座、桂喜久男は林家喜久藏になった。正規の最初の師匠は三木助だが前座修行を半年しただけで師匠は逝った。未亡人は「看病をするために入門したようなもの」と気の毒げに語ったという。キクちゃんの師匠はその物まねが得意な彦六正藏でいいのだろう。
このとき、後に四代目桂三木助を継ぎ、四十一歳で自殺する五代目小さんと同じ名前の小林盛夫はまだ三歳だったのだなと感慨をあらたにする。三木助五十七歳。可愛いさかりの子を残して、三木助もまだ死にたくなかったろう。
---------------
脱線して。
まったく日本語ってのは最後まで読まないとわからない文だからたちが悪い。上記の文は「四十一歳で自殺する小林盛夫はまだ三歳だった」が主文である。しかしそこに「五代目小さんと同じ名前」との情報を入れようとすると、「四十一歳で自殺する五代目小さん」になってしまう。
それを避けるなら、「後に四代目桂三木助を継ぎ、四十一歳で自殺する小林盛夫はまだ三歳だったのだなと感慨をあらたにする」とし、あとに「桂三木助が親友だった五代目小さんと同じ名前にした愛息である」とでも附け足せばいい。
しかし日本語の感覚としては最初のわかりにくい文章の方が自然になる。私もすなおに書いたらそうなった。だが今までにも他者の文でも何度も何度もいらだってきた形ではある。最初の文を素直に書けるのに敢えてわかりやすいように直しつつ書くというのも不自然だと思う。どうすればいい。「他者にやられてイヤなことは他者にするな」の原則を守るなら、私は自分の文からこのわかりにくい文を消さねばならない。
---------------
●色さんとの交友
柳朝は雀荘で「色さん」と知り合う。照藏時代だ。阿佐田哲也こと色川武大さんである。その後の新人文学賞を受賞するころや、麻雀小説の阿佐田哲也となって活躍するころの交友がリアルタイム進行になっていて楽しめる。とはいえ親しく交友していたわけではなくめったに会わない。伏線としての色づけである。
色川さんが江戸前ことばの柳朝を好んだことはわかりやすい。私の知識だと色川さんというと談志なのだが、始まりは柳朝のようだ。志ん朝のあまりに早い出世に談志(当時小ゑん)が憤っていることを柳朝から聞いて、色さんが「小ゑんさんか、あの人、好きだなあ」と言う場面がある。
---------------
●日曜演藝会
日曜の午後一時十五分から二時までNET(現テレ朝)がやっていた寄席番組である。末広亭からの中継。毎週見ていた。
大喜利のメンバは、柳朝の他、米丸、小せん、柳好、馬の助、夢楽。私には「大喜利」というと『笑点』より先にこれが浮かぶ。視聴率30%の人気番組だった。というか前にも書いたが当時のNETには寄席番組と洋画しかなかった。
司会は馬場雅夫。当時も今も落語通であり、落語に詳しい司会者というと真っ先に名が浮かぶ。
いまマニアックな落語番組の司会進行というと最も有名なのは玉置宏だろうが、二十年前、深夜のTBS「落語特選会」で彼を見たときは奇妙に思った。というのは当時この「日曜演藝会」の裏番組(一部が重なる)である「ロッテ歌のアルバム」で司会をしていたのが「お口の恋人 ロッテ提供 ロッテ歌のアルバム、一週間のご無沙汰でした。司会の玉置宏です」と登場するおしゃれな司会者の玉置だった。落語とは結びつかなかったからである。今はたいへんな落語通として敬愛しているが。
この番組は、色物ありの盛りだくさん45分の中継である。『笑点』のように売りは最後の大喜利だ。とするなら言うまでもないが、まともな落語などない。古典の大ネタなどあるはずもない。まああったにしても田舎の子供である私に理解できたかどうかは疑わしい。
でもこの当時、寄席中継はいっぱいあって、いくらでも見られた。娯楽がそれしかない時代だ(笑)。「ちはやふる」を初めて聞いたときのことはよく覚えている。演者は誰だったろう。桂伸治か。
べつに心に残る想い出の番組というほどではないが、この本で思い出し、懐かしく思った。
---------------
●四天王の変遷
昭和三十八年。立川小ゑんが立川談志となって真打ちに昇進する。三十三歳の柳朝、三十歳の円楽、二十七歳の談志、二十五歳の志ん朝が若手四天王と呼ばれた。
始まりは矢野誠一がこの四人を褒め「四羽烏」と書いたことだそうな。三羽烏であり四羽烏はおかしい。だったら四天王だろうと定着する。
しかし私のより強く記憶しているのは柳朝の代わりに円鏡が入っている四天王である。そのきっかけがこの本にはあり勉強になった。なんでも「落語界」という雑誌にどこかの放送ディレクタが「私は四天王は談志、志ん朝、円楽、円鏡だと思う」という柳朝を外した四天王にか関する論文(?)をしつこく書いて、いつしか世の中をそっちに引っ張っていったという。
始まりは昭和五十二年。「落語界」創刊が四十九年だそう。「談志、志ん朝、円楽は問題ないとして、あとのひとりに、柳朝をあげる人もいれば、小三治、円窓の名を挙げる人もいる。しかし私は円鏡を」という論陣だったようだ。
---------------
●日曜ワイド笑
昭和四十四年、開局したばかりの東京12チャンネルで始まった演藝番組。柳朝はレギュラだった。これ、「寄席中継番組」となっているがどこからの中継だったのだろう。あんまりおもしろくなかった。
それに私もすこしは色気づき、落語番組は古くさいものと拒み、キョセンの「ビートポップス」なんぞを楽しみにする齢になっていた。クリームの「ホワイトルーム」、ビートルズの「オブラディオブラダ」あたりのころか。
ショーに「笑」を当てるなんてのはこのころから好きだったんだな(笑)。
---------------
●しろうと寄席
これはフジテレビ。玄人ぶったしろうとの藝を見るというのはむかしからあまり好きではなく熱心に見ていなかった。でもこまっちゃくれたガキが上手に落語を演じ、審査員の文楽に褒められていたのは覚えている。あれがのちの小朝だったらしい。地味で小柄ななじいさまとしか思わなかった文楽の落語をそれから三十五年後に真剣に聞き返すようになるとは思わなかった。
---------------
●アップダウンクイズ
柳朝、夢楽組が優勝したときのことはよく覚えている。一人乗りのゴンドラに二人詰め込む「藝能人大会」は度々やっていた。それにしても十問正解して「夢のハワイ」の時代である。遙か彼方。目薬のロート製薬が提供だった。あんなつまらん番組をよくもまあ毎週見ていたものと自分が悲しくなる。
「スパイダース、タイガース、ジャガーズ、さてこれらの動物の足を全部足したら何本?」という問題が出たときは会場からも失笑が漏れたものだった。
---------------
●談志立候補
昭和四十五年十一月二十五日、三島由紀夫割腹自殺。
化学の先生が「たいへんだ、三島由紀夫が自殺した」と言って教室に入ってきたときのことは覚えている。私は高三だった。
昭和四十六年、立川談志参議院選立候補。
黒門町に行き、「文楽師匠、応援よろしくお願いします」と選挙カーから言うと、二階の窓が開き、「談志くん、ようがすよ」と師匠。いい話だ。
応援の三平が談志の名を言わず「三平です、林家三平です」と連呼するものだから台東区では三平に50票以上入ったという実話は笑える。
立候補前、談志は石原慎太郎を伴って落語協会の後援を要請する。圓生その他の幹部が承知する中で唯一林家正藏のみ反対する。彦六正藏は共産党支持である。正藏は選挙期間中も熱心に共産党の応援演説をしたという。
正蔵(彦六)は、かと思えば藝術祭賞を受賞したときは「銀メダルばかりだったので金メダルが欲しかった」と大泣きしたというし、よくわからん人だ(笑)。
この「銀メダル」には「小さんが金メダルなのにそれを取れず銀メダルの他家の正藏を継いだ」も含まれているのだろう。落語協会も副会長までで会長にはなれなかったし。
私はこのとき大学一年生。談志の選挙カーを見ている。
音楽に夢中で見ていた演藝番組は『笑点』ぐらいになっている。
この本で知ったのではないが、談志の息子の名は「慎太郎」と知る。談志本の中に石原慎太郎はしばしば登場するし、選挙出馬もその影響なのだが、まさか我が子の名にまでとは知らなかった。
---------------
●文楽絶句
昭和四十六年八月三十一日、文楽が絶句して「勉強し直して参ります」と高座を降りる。国立劇場。
四ヶ月後の十二月十二日、死去。この三日前にりん夫人を亡くしていた志ん生は、もうだめなのではないかというほど落ちこんだという。この立て続けの死は利いたろう。
---------------
●分裂への序曲
昭和四十七年三月。圓生が会長の座を小さんに譲る。このとき副会長の正藏を一緒に辞去させたいが正藏は会長になりたいのが見え見え。正藏の性格を知悉していた圓生は、会長になって欲しいと正藏にもちかける、一度目だから正藏は遠慮する、もう一度進められたら受ける気でいる。圓生それをせず、「ああ、そうですか」と引っ込めてしまい、小さん会長誕生。圓生の策略成功。
その小さんに「ああたの好きなようにやりなさい」と言う。小さん、今までとは違った斬新な運営方針を打ち出す。その方針の違いがのちの三遊亭獨立騒動につながる。
---------------
●十年闘病
柳朝が脳血栓で倒れたのが五十一歳。十年の闘病を経て六十一歳でなくなる。復帰は適わなかった。それどころかことばは最後までもどらず、字盤を指さしての会話だったという。
あらためて志ん生や三平の復活の奇蹟を思った。体の自由は奪われたが頭脳の明晰さは残った。たけしの事故の時も同じ事が言われた。
-------------------------------
つまらない文章であり、物語として読んだらおもしろくないとひどいことを言ってしまったが、こうして勉強になったエピソードを並べるだけでも価値のある本だと思う。
ただ、そういう資料本としての価値のような褒めかたは著者としてはすこしもうれしくないだろうから、失礼な褒めかたはしないことにする。
|