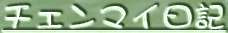 

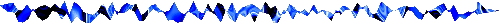
 チェンマイのお堀。 チェンマイのお堀。
美しい旧市街の景観を壊しているビルは、この日記の舞台である99年当時は、雑居ビルの予定で建設されていたが、バーツ下落のため建設が途中で中止になり、骨組みだけの幽霊ビルと呼ばれていた。01年から工事が再開され、02年3月、ホテルとなって開業した。
新『サクラ』はその裏手にある。ぼくがチェンマイ市長なら、景観を乱すこんなビルは建てさせないけどね。

有山パパのアパートへ、本を借りに行った。
毎回チェンマイでの滞在日数、そこでの行動と読書に取れる時間を計算して、十分と思われる量の本を持ってくるようにしている。外国にいるとき、日本食にも日本語にも人肌にも飢えることはないのだが唯一活字だけは例外になる。東京でも田舎でも毎日本屋で二時間以上は過ごしている。行かない日はない。田舎だと一店にあまり長くいるのは恥ずかしいので、いくつかの店を巡回訪問である。
本屋に並んでいる本でその町の文化水準が解る。恥ずかしいことだが我が故郷のレヴェルはとても低い。それでもよくしたもので田舎の書店は、それぞれが得意分野をもっている。どこにでもあるのはクルマ関係の雑誌とエロ本だが、中にはなぜか宗教関係の本が異様に充実していたり、店舗とは不似合いな岩波新書が勢揃いした店があったりする。田舎のいくつかの町の本屋をクルマで移動するのだから毎日六十キロぐらいはそのためだけに走っていることになる。顔なじみになった店員は、私のことを毎日よく来る人だと思っているかもしれないが、本当は来すぎて恥ずかしいからあちこちの店に移動しているのだとまでは知るまい。この移動時間と車中で聴く音楽が私の憩いの時間になる。ここでアイディアを練るのだ。本来憩いの時間とは、きちんと仕事をしたものに与えられる休憩のことなのだが、私の場合、一日中憩いの時間だったりもする。
ハードカバー、ペーパーバック、文庫本、月刊誌、週刊誌、漫画本と種々雑多であるが、一年三百六十五日、本を買わない日は一日とてない。パソコン雑誌なんて月に二十冊は買っている。漫画雑誌を買う量がさすがに齢と共に減ってきたのでこれ幸いと思っていたら、その隙間にパソコン雑誌が入ってきた。元の木阿弥。呉智英さんのようにゴミ箱から雑誌を拾う勇気のない私には、この辺の出費もばかにならない。さらには本を読みながら飯を食ったり酒を飲む悪習がいつの間にか身についてしまった。活字のない環境におかれるのが一番辛い。
旅先でも活字切れにならないよう、細心の注意を払っているのだが。

昆明の市街。北京路の歩道橋より。
今年の春、中国に行ったとき、−−私はチェンマイのアパートに、あのゴロゴロ引っ張る大型スーツケースで乗り込み、そこから最低限必要なものだけを肩掛けバッグに入れ軽装になって出かけるのだが−−なんの手違いかその肩掛けバッグに入っていた本が文庫本二冊だけだった。それで辺境の地に十日間滞在したものだから、活字に飢え、さして好きでもないその本を、何度も読み返すはめになった。好きな本や映画を何度も繰り返し読む、観るという人は多いようだが、私は一回きりの方である。映画「タイタニック」の話をすると、必ず女性から「何回観たか」と問われる。一回に決まっている。あんなもの何度も観るほどのものじゃない。
一回きりしか読まない本の内容はどこまで心に刻まれるのだろう。たまに自分の部屋にある古い本を手にして読み始め「おお、なんておもしろいんだ。今まで買ったまま読まずにいて損をした」と悔やんだりすることがある。半分ぐらい読んだところで、どこかで一度読んだようなという気がしてくる。結末近くになってやっと昔読んだ本であることを思い出す。一度読んだ本を新たな感動で読めたから、なんか得をしたような気分でもあり、一度読んだものをここまで忘れてしまうものだろうかというなさけない気分でもある。
人間には忘れるという能力があるから生きていられるのだと言う。たしかにそうだ。あの身悶えするような恥ずかしい過去を、あれもこれも全て覚えていたならとてもとても生きてなどいられない。私は記憶力がよく、幼い頃の話や学生時代の話を友人としても、当時の事に関する記憶では人後に落ちないのだが、恥じ多いこの人生を今まで生きてきたのだから、忘れるという能力の方もなかなかのものであるのだろう。物忘れがひどいなどという言いかたはマイナス思考だ。「忘れる能力」と考えるのが良い。
そういう発想から生まれたのが、赤瀬川源平さんや東海林さだおさんが始めた「老人力」なのだが、どこかで勘違いされたまま、むしろ「豊富な体験のある老人達の知識経験の力」のような間違った解釈の方が普遍してきたのは困ったものだ。
三十歳の時まで学生時代から買い溜めた本を大切に持っていた。それが私の生きてきた標(しるし)のような気がしていた。ある日そういう自分に腹が立ち、本を捨てる。いかにして生くべきか悩んでいたその時の私には、既に読み終えた本を大切に持っているというそのこと自体が、通り過ぎた過去にしがみついている醜態のように思えた。分野別作家別にきちんと整理された本棚こそが唾棄すべき過去の象徴に見えた。自分を変えるためにはまずこの本を捨てなくてはダメだと思ったのである。段ボール箱十箱以上の本を捨てた。
いま思う。もったいないことをしたと。もしもそれらの本のパワーが私の血となり肉となっていたのなら、それは過去として切り捨てられる。だが自分の記憶能力というものを考えると、あれらの本はほとんど私の中に入っていなかった。齢を取ってから、ゆっくりともう一度読み返すことが出来た。完全に忘れているものもあるだろうし、半分ぐらいは覚えているものもあるだろう。それぞれの味で購入した当時を懐かしみつつ読書を楽しめたはずである。短気はいかん。でもそういう思い切ったことをしてでも自分を変えねばと、あの頃は悩んでいたのだった。
中国で過ごした今年の春、本も映画も一回きりの私が二冊の文庫本を何度も読み返した。初めての経験だった。
一冊は分野別の良書案内のようなもので、これは読み返すほど勉強になった。
もう一冊は史上初の乱歩賞と直木賞をダブル受賞したという作品で、既にハードカバーで読んでいたものだった。その当時の読書日記には「とてもおもしろい」と評を書いたことを覚えている。なのに活字に飢えた中国で何度も読み返していると、次第にその傑作であるはずの作品に粗(あら)が見えてきたのである。「あれ? この表現て、たしかさっきもあったよな」と思う。一回しか読まないならストーリィを追うことに夢中になっているから気づかない。假に気づいたとしても、先に進みたいので振り返ったりはしない。しかし読むもののない中国辺境の地で繰り返し読んでいると、前のページにもどって探してみたりする。何回目かの読み直しの時など、暇にあかせ同じような表現の乱発に色塗りをしてチェックしていた。(こりゃひどいな、このパターンの会話は今度で五回目だ)などと思いつつ。初めて読んだときから世評ほどの傑作とは思っていなかったが、ひょんなことからそれを確認したのだった。
これは決して意地悪な見方ではない。一回しか読まない主義の私にも何冊かの複数回読んだ好きな作品はある。それらにそんな缺陥は発見されなかった。読むたびに新たに感動した。この本は、初めて読んだときから喉に小骨が刺さっていたというか、なぜか気になる箇所があった作品だった。それが繰り返し読みによって確認されただけである。作品の方に問題がある。作者の推敲が足りないのだ。
私は映画もレンタルヴィデオも一回しか観ない。でもこれもまた繰り返し観ることには新たな発見があるらしい。そういう趣旨の本に書いてあったことだが、かの「インディ・ジョーンズ」なども、何十回も観ていると「ずっと洞窟の中に閉じこめられているはずなのに、カットが違うと、ハリソン・フォードの着ているシャツの模様が替わっている」なんて箇所があるらしい。映画は細切れで作ってゆくから、現場の誰もが気づかないそういうミスも起きるのだろう。
チェンマイに持ち込む本には毎回私なりのテーマを決めている。「日本では読まない本」だ。偏食の子供でもお腹が空いたら嫌いな人参を食べるように、活字に飢えるチェンマイでの時間を、読まねばと思いつつ読んでいない分野の本を読むように無理矢理し向けるのである。時代小説と呼ばれるものを読むようになったのも、このチェンマイでの読書のお蔭だった。何故に江戸時代などを舞台にした小説が未だにひとつの分野として存在するのか、読みたいとは思わないが、その商品としての存在価値には以前から興味があった。熱心にあれこれと読んでみて解った。あれは時代小説という名の現代小説なのだと。故きを温ねて新しきを知るとは違う。古い時代設定の中で動いているが、すべては今なのである。
最近は「作家シリーズ」をやっている。ひとりの作家のまとめ読みだ。今回は東野圭吾の本をまとめて持ってきた。私は推理小説が好きではない。一通りのものは読んでいるがマニアックな人たちと議論できるレヴェルにはない。東野圭吾も一冊も読んでいなかった。ちょうど「秘密」で推理作家協会賞を受賞し、今年ブレイクするのではとマスコミで話題になっていたから、今回の夏休みでものにしてしまおうと思ったのだ。ハードカバーの「秘密」と、各社から出ている文庫本を買い揃えてきた。
イミグレーションでたまに「中身を見てもいいですか」と手荷物を検査されるとき、私のスーツケースがとんでもなく重いと驚かれる。中身はびっしりと詰まった本である。文庫本を詰めこむとかなりの重さになる。それでも私が物書きだと知るとみな好意的に納得してくれるから本にはまだそれだけのステイタスがあるのだろう。衣類その他はチェンマイで買えるが本だけは日本から持参しなければならない。
宇宙堂のナベちゃんが古本屋を開くにあたって、自分の蔵書と買いそろえたものを船便で(日本からチェンマイまで)送ったとき、安いはずの船便なのに、重かったからか、ずいぶんと高い値段だったと言っていたっけ。本のことがテーマなので宇宙堂を無視して通りすぎは出来ない。
タイに夢中になり、年に何ヶ月かをチェンマイで過ごしていた頃、宇宙堂の本を読み漁った。心のオアシスだった。しかも日本人的心をもっているナベちゃんは、百バーツの本を読み終れば五十バーツで買い取ってくれたし、日本から持参した読み終った本をプレゼントすれば、なにか好きな本を一冊持っていっていいよとも言ってくれた。ナベちゃんの心意気に惚れ、宇宙堂に日参していたものだ。
ここのところご無沙汰しているが、それは今回ここに書いたように「読もうと思いつつ読んでいない分野」「ひとりの作家」のようにテーマを決め、日本から本を持参するようになったからである。
最初の頃は、チェンマイにいられるだけでよかった。それでも回数を重ねていれば、チェンマイにいる時を利用して何かを身につけようという意識が芽生えて来る。
旅というものは慣れるほどに軽装になるという。そんな話を読んで、旅慣れていない私は、先達に従おうと可能な限りの軽装を試みた。しかし自分なりの流儀が出来てくると、なにもそんな他人の流儀に従わなくてもいいのではないかと思えてきたのだった。ヘアトニックやアフターシェーブローションも、現地調達するようにしていた。チェンマイなら何でも揃う。でもやはり使い慣れた香りのものがいい。私は居直った。おれはおれの流儀で旅をすると。日本からわざわざいつもの製品を持参するようになった。訪タイする回数が増えるたびに私の荷物は大きくなっていった。持参する文庫本はほんの数冊から、いつしか何十冊にもなっていった。自分の読みたい本に飢えて苛々するより、どんなに重くても必要なものは持参しようと発想を切り替えたのである。宇宙堂とは疎遠になってしまったが、一応職業物書きとしてのそういう理由なのでご容赦願うしかない。
さてまた東野圭吾の話。話題になっている「秘密」だが、これは小説の出来不出来以前に、「娘の中に妻が宿るという設定の勝利」だろう。父親にとって永遠のテーマである思春期の娘との関係を、その肉体に妻の精神が宿るということで、うまくくすぐっていた。男ならこの設定に揺れない人はいない。でも小説としては読み応えがなく物足りなかった。妻である娘に嫉妬するシーンや、娘の中から妻が消えてゆくシーンなどでは、もっともっと浅田次郎風に泣かせて欲しかったと思う。まあ、そういう書き手ではないんだろうけど、東野さんという人は。
今年の夏の読書で、東野圭吾についてしゃべれる最低限の資格ぐらいは出来たと思う。そのことにさして意味はないし、これからも私が彼の熱心な読者になるということはないだろう。でもいつかどこかで彼のファンと会ったとき、会話を交わすための基礎知識は身に付いたことになる。それがうれしい。一夏の成果である。
東野圭吾の本の他にも豆知識的に勉強になるような本を何冊かもってきていた。量は充分のはずだった。それが十日間のはずの中国に予定変更で二十日間も滞在したものだから計算が狂ってしまった。大理市や景洪市などで読書に励みすぎ読み尽くしてしまったのである。
せっかくの旅先なのだから日本語の読書よりもその地の人と交わるべきという意見もあろうが、とにかくもう漢民族とは絶対に合わないということが解っているので、なるべく関わらないようにせざるをえない。旅に出ることにはプラスもマイナスもある。知らない頃は文化的先達として尊敬の念を抱いていた漢民族を、顔を見るだけでうんざりするほど嫌いになったのは、プラスなのだろうかマイナスなのだろうか。せっかくの尊敬の念が消えてしまったのだからマイナスという考えもあろうが、知りもせずにイメージだけで尊敬しているよりは、正しく知って嫌った方がよいのではとも思う。
旅行作家下川祐治さんの名言に「漢民族の悪口ならいくらでも言える」というのがある。中国旅行でさんざんひどい目に遭った彼が、文中に書いたひとことを私が勝手に名言と決めつけているだけだが、まったく漢民族というのは日本人の常識からは計り知れない人種である。接したら誰もが彼我の差を知るだろう。中国が大好きで何年も留学していて、それだけでは物足りなく、帰国後も足繁く中国に通っているという日本人もいたりする。私には理解不可能だ。漢民族に対してストレスが溜まらないということは、その人もまた漢民族的な人なのだろう。たぶんその人と私は合わない。
中国の中でも雲南省は特殊な省である。少数民族の自治県が多く、大理市は白(ペー)族、景洪市は泰族の県であり、日本人には過ごしやすいところだと言われている。その通りなのだけれど、それでもやはり要所要所では漢民族がでかい顔をしていて、いきおいなるべく接したくないということになり、部屋の中での読書がすすむのであった。
大理古城(日本的に言うと、旧大理町)には日本人の集まるカフェ(という名の食堂)があった。見るからにバックパッカーぽい青年達が彼ら特有の佇まいでチラっとこちらを見る。世界中どこでも同じである。笑えるよねえ、彼らの幼稚な縄張り意識と警戒心は。彼らからすると、自分たちと同じ臭いのしない、それでいて観光客のようでもない私は、判断しづらい警戒すべき対象なのだろう。私もまたバックパッカーは嫌いなのでちょうどよい。日本で稼いだ金で異国の果てに滞在し、異国の果てにいるというそのこと自体をアイデンティティとしている若者よりも、私は日本でバリバリ働いている若者の方が好きだ。
この種のカフェには、庶民的な中国の食堂では珍しい冷えたビールがあったし、大理古城には白人観光客が多いからかフライドポテトのような有り触れた(でも中国では珍しい)つまみもあって、それらを飲み食いしつつそこにある日本語の本を読むことは楽しかった。ここに出入りしたお蔭で私の活字飢えはだいぶ癒された。なぜか70年代に発行された政治的な本(例えば加瀬英明さんの作品)があったりして、かなり充実した時間を過ごせたのである。二十年ぐらい前に発行された政治経済の本を読むというのは(もちろん良書に限るのだが)、答が既にいま出ているので、とても興味深く読めるのだった。
中国から帰ってきて最初の二、三日はストレス発散とばかりに遊び呆けていた。これはかなり問題で、中国から帰ってきたばかりのチェンマイでは、お恥ずかしい話、とてもここには書けないようなことを私はしている。といってそれは身の下の話ではない。朝からビールを飲み、昼からマッサージに三時間もかかり、夜はオープンバーを飲み歩いた後、何時間もスターシックス(ゴーゴーバー)に入り浸ってボケーっとしているというようなものだ。とにかく自堕落な生活を送る。それが楽しくて楽しくてしょうがない。とにかく私は、中国はダメだ。
身の下の話といえば、中国の売春事情というのはとんでもないことになっている。いやはやなんとも呆れ果てた。それはまた別項で書こう。
しばらくは遊び呆けるのだが、しょせん空腹の時の大食いのようなものだから、すぐに満腹する。満腹すると興味がなくなる。するとまた永遠に満腹することのない活字飢えというものが頭をもたげてくるのだった。
それでパパのところまで本を借りに行ったのである。

デジカメ写真を探してみたら、冒頭の写真解説で書いた「幽霊ビル」と呼ばれていた当時の写真が出てきた。この姿のまま何年も工事が止まっていた。今となっては貴重な写真になる。
 
|