|

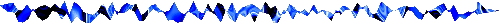
●願ったり叶ったり

朝十時。『サクラ』で会ったYさんに「今夜、焼き肉を食いに行かないか」と誘われる。この人はケチだ。酒も飲まない。飯を食うのも早い。でもその後は長い。きょうもいつものオムライスを食った後、紅茶を飲みつつもう二時間も居座っているらしい。こんな人と飯を食いに行っても美味いはずがない。行きたくない。
「いやあ、ぼくは酒飲みだし、新聞読んだりしながらゆっくりと食べるんですよ。料理もいろいろ頼みますし、待たせたら悪いですから」と婉曲に断る。
「いや、そんなことは関係ないんだ。ぼくはぼくの好きなものを食べるだけだからね。あなたはあなたの好きなものを食べて好きなだけ酒を飲めばいい。そういうことだ。それじゃ何時にする?」
無神経な人には遠回しでは通じない。「あんたと一緒に食べたくないんだよ」と言えばそれですむのだが、おれはそれが言えない。コンピュータ・プラザにCDを受け取りに行くのが四時半だと言ったら、「じゃあ『北門』で五時ね」とかってに決められてしまった。
憂鬱だ。はっきり言っておれはこの人が苦手なのである。毎日バイアグラを飲み昼夜を問わず置屋に通い詰め、目が疲れたからビタミンAを飲む、ちょっと体がだるいので朝鮮人参の粉末を飲む、ビタミンEがどうのこうの、足がだるいときはこれだ、腸がすっきりしないときはあれがいいと、朝から晩まで薬の話ばかりしている。これもチェンマイ名物コナ中毒と同じ別種のドラッグ中毒の一種だろう。二十四時間、自分の体の栄養素と精子の製造具合だけを考えて生きているこの人にとって、たぶんきょうは肉というタンパク質を補給する日なのだ。そんなことに付き合いたくない。なぜたいして親しくもないおれを誘ったのかという理由は簡単で、彼の数少ない置屋通い仲間は彼以上のドケチばかりだからである。焼き肉屋なんてのはアルマゲドンの前日でも行かない。それどころかアルマゲドン当日でも銀行の利子の計算をしているような連中ばかりだ。
一緒に行くことになってしまった以上は、おれはいつものスタイルで食い、彼との違いを明確にするしかない。それで次回から誘われないようになれば願ったりだ。
*
五時、『北門』に行く。おれはいつも通りの注文をする。
昨夜、ロータリーで有山パパに「『北門』によくひとりで行くんですけど、700バーツはかかりますね」と言ったら、「ええー! ぼくがシーちゃんとシーちゃんの両親を連れて四人で行って、お腹一杯食べて800バーツだったよ」と、とても信じられないという顔で言われたので、おれのこの日の注文を値段入りで書いておこう。
並カルビ120B、タンシオ120B、キムチ50B、ナムル50B、オイキムチ50B、サンチェ50B、ビアシン100B、並カルビ追加120B、ビアシン追加100B、仕上げに冷麺100Bで、合計860バーツである。何故かおれの大好きなカクトゥギがないのが『北門』の缺点だ。べつに大食いじゃないだろう。ご飯を食べていないし、これぐらいは入る。ビールと肉で腹八分目になり、最後に冷麺で仕上げてちょうどいい。日本でもほとんど同じ食べ方なので値段の比較がしやすい。日本でこれだけ食べるとだいたい一万円だ。チェンマイだと二千五百円。物価の差は四倍ということになる。もっとも日本人向け焼き肉屋というとても特殊な店なので、こんな比較は無意味かも知れない。それでもおれにとっては、日本で一万円の焼き肉がチェンマイなら二千五百円で食べられるという目安にはなる。
長々とメニューを見て気を持たせた後、Yさんは一番安い「焼き肉セット」を注文した。飲み物は「水」だ。ミネラルウォーターを注文しなければならないと覚悟していたのに、この店は水がタダだと嬉しそうに言う。ケチな人はタダのものを見ると、ほんとに嬉しそうな顔をする。彼らの表情でいちばんいい顔だろう。盛り合わせ焼き肉とご飯と味噌汁のセットである焼き肉セットが届くと彼は勢いよく食べ出した。おれが『バンコク週報』を読みつつ、ビアシンを一本空ける頃には、もうすべてきれいに食べ終っていた。デザートの果物(もちんセット内の一品)も片づけ、すっかり手持ちぶさたになっている。
向こうが誘ったのだし、おれがゆっくり食おうが全然気にしないという言質もとってある。気にする必要はなかった。だがテーブルにあれやこれやと並べ、ビールを飲み舌鼓を打っているその前に、何もすることのない五十男が茶をすすりつつ座っているというのは、くつろぎとはほど遠い。
それでもおれは、気の弱い男だからこそここで妥協してはいけないのだ、誘ったのはあちらだし、そのときに好きなようにやってくれと言われているのだからと自分を励まし、いつものよう、もう一本ビアシンと追加のカルビを頼んだ。意地でもいつものおれのままでいようと思った。彼もさすがに自分から言い出したことだからか黙っている。先に帰るとも言い出さない(帰ってくれた方がありがたかったが)。
そこに『北門』のマネージャーのワットさんが来る。ワットさんは錦糸町の焼き肉屋で八年間働いていた。経歴はチェラロンコン大学卒業という異色の人である。日本の東大に当たるタイでいちばんの大学だ。タイでの価値は東大以上だろう。タイの会社を辞め一旗揚げようと日本に行ったが、仕事は焼き肉屋の店員ぐらいしかなく、八年間で溜まったお金は「ちょっとだけね」と苦笑する。日本語が堪能なことからスカウトされてこの仕事をしている。おれは初めてきたときから親しくしてもらっていた。
ワットさんと話が始まる。ヴェテランウェイトレスのワーも来た。みんな辞めちゃったから知っている顔はワーだけだよと話す。パタヤの先、ラヨーンに新しい店を出すため、そちらに出掛けている神谷社長に、ワットさんが携帯電話をかけてくれる。神谷さんと長電話したりして、益々おれの飯の時間は長くなる。タイ語も話せず、ワットさんや神谷さんとの交友もないYさんは何もすることがない。ひたすらおれの食事が終るのを待っている。やはり一緒に来たのは間違いだ。もうこんな関係は嫌だと思った。あちらもつまらないだろうが、こちらだってたまらない。これじゃせっかくの焼き肉が栄養にならない。複数でご飯を食べるなら、気の置けない仲間とわいわいやるのがいい。こんな人と来て気まずい思いをするのなら、ひとりで来て新聞でも読みながら食った方がましだ。
なんとか食い終った。針のむしろだった。もうこんな気まずい時間はいやだ。
「会計はべつべつね」とYさんが言い、焼き肉定食代190バーツを払う。しっかり10バーツのお釣りをもらった。おれは860バーツに900バーツを払い、釣りをもらうかチップにするか一瞬迷い、結局チップにした。
つまらんことに迷ったのは、ウェイトレスの出入りの多い『北門』では今、まともな給仕が出来るのは、ワットさんとワーだけなのである。後の女性達は見習い中である。おれが来たとき、ワットさんは夕方の休憩中でいなかった。ワーは他の客に付いていた。おれのところに来た新人の娘は、おれのビアジョッキにビールを注ぐとき、派手にビールを吹きこぼした。その泡はテーブルを伝い、おれのズボンを濡らした。それはしょうがない。そのことには怒らない。だがこの娘は何を考えているのか、ビールが吹きこぼれ、おれが慌ててズボンを拭く様子を見て、「くすくす」と笑ったのである。まるで他人事のようにだ。おしぼりを持ってくるわけでもない。ごめんなさいでもない。ナプキンでズボンを拭くおれを見ながら、くすくすと笑いながら我関せずと去っていったのである。おまえの注ぎ方が悪くてビールがこぼれ、客がズボンを濡らしたんだぞ。謝るのが礼儀だろう。どういう精神構造をしているんだ。テーブルにこぼれたビールをナプキンで拭き、びしょ濡れのジョッキを拭いながら、なんでおれがこんなことをしなけりゃならないんだと、おれは腹の中で毒づく。まったくタイ人てやつは。
このニサイ・コンタイ(タイ人気質)をタイのデパートなどでやられても許す。それがタイ人であり誰もがそうなのだから怒ってもしょうがない。ある種のおおらかさでもある。ここはタイだ。文句があるなら自分の国に帰りなってなもんだ。
だがここは日本人神谷さんの経営する『北門』だ。日本人の常識が通用する空間のはずだった。おれはワーを呼び抗議したくなる気持ちを懸命に抑えた。こういうことがたびたび起き、神谷さんやワットさんが新人のタイ人ウェイトレスに注意する。すると翌日からぷいと来なくなってしまう。ウェイトレスのいつきが悪い。日本人向けの厳しいマナーをクリアして一年後の今も勤めているのは、チーフ・ウェイトレスのような立場にいるワーひとりだけなのだった。おれがここで怒り、それが原因でウェイトレスがひとり辞めたなんてことになったら神谷さんに会ったときばつが悪い。神谷さんは鷹揚な人だから、「いやいや怒って当然ですよ。そんな態度の悪いのは早く辞めさせてもらって助かりました」なんて言ってくれそうだけど、とにかくここは丸く収めようとおれは我慢したのだった。
それが一瞬ではあるがチップをおくかどうか迷った理由になる。チップに関するおれの基本は、納得したサーヴィスにはたっぷりとあげる、不愉快な思いをした店では一銭もおかないというものだった。チップという制度の発祥地であるヨーロッパでは、チップだけで生活している連中もいるからか、自分の担当テーブルに関しては、笑顔を振りまき、完璧なサーヴィスをしようとする。気分がいい。食費の二割ぐらいのチップなんて全然惜しくないほどだ。ところがタイでは、客に対するサーヴィスとは関係なく、単に客は釣りの小銭は置いて行くものという悪い形でチップ制度が定着してしまった。そこのところがどうも釈然としない。
笑顔で迎えてくれたワーにあげたと思えばチップは当然だ。でもこの小銭は彼女に行くのではない。チップは溜めておいて後でみんなで分ける。おれにビールをこぼして笑っていた娘の取り分にもなるのだ。だからおれは迷ったのだった。
翌日も翌々日も『サクラ』でYさんとはニアミスしたが、彼は『北門』でのことは何も口にしなかった。誰かに愚痴ったということもないようだ。でもおれが長々と時間を掛けて食い、知り合いと話したりするあいだ、ただじっと待っているだけという体験は、彼に何かを考えさせたようだった。それ以後、おれはYさんから誘われなくなったのである。願ったりが、叶ったりになった。
今までなら『スポットライト』に誘われたような場面でも、誘おうとした彼が、何かを思いだしたように思い留まることがあるようになった。コーラ一杯で二時間粘る彼とビールをがばがば飲むおれでは一緒にいても盛り上がらない。おれは気に入った女にはこちらから飲み物を勧めるが、彼は女からねだられても絶対に奢らない。それはどちらが正しい悪いではない。Yさんはおれから見るとケチで遊び方を知らない人だとなるが、あちらから見たらおれは無駄な金をばらまくバカ日本人の典型となるだろう。それぞれのやりかただ。ただ楽しくやるためには、似たようなタイプで行った方がお互いのためだということである。それまで彼は、おれと一緒に行くと通訳代わりに使えて便利だと思っていたようだが、どうやらそれ以上のマイナスが自分たちのあいだにはあるとやっと気づいたようだった。いいことである。
*
Yさんは.小金持ちで何千万円も貯金があるらしい。なのにあんなにケチケチして何が楽しいのだろう。いやケチだからこそ無役のサラリーマン時代に何千万円も貯められたのか。おれは貧乏人だ。借金はあるが貯金はない。金って何だろう。チェンマイ・チェンライ・メーサイに巣くう風采の上がらないドケチオヤジ達は、みな何千万円もの貯金持ちらしい。わからん。それであんな耐乏生活をして何が楽しいのだ。
いやな思いもしたが、嫌いな人と縁が切れたようだ。目出度い。
●日本食堂における飲食費について
「日記・1−1」に『サクラ』と『ゆみ』が、上文に『北門』が出てくる。私のチェンマイにおける日本食堂での一食の平均を並べてみると以下のようになるようだ。手帳のメモを見ながら計算してみた。
『サクラ』 350B
『ゆみ』 450B
『フジ』 550B
『北門』 750B
『赤門』 1200B〜2500B
文章を読んでいただけば解るように、私はいつもビールを飲んでいる。これらの値段はつまみを何品も取ってビールを飲み、最後に何かを食べて仕上げるという酒飲みの飲食費平均である。酒を飲まない人の参考にはならない。
ほんの少し役立つものがあるとしたら店毎による金額差であろうか。私の飲食というのはバラエティに富んでいるようでいて実はワンパターンである。だいたいつまみを三、四品頼んで、ビール大瓶二本を空け、最後にうどん、カレーのようなもので閉めるというものだ。そういうワンパターン飲食で、『サクラ』よりも『ゆみ』が百バーツ、『ゆみ』よりも『フジ』が百バーツぐらい高いということは、メニューにある値段に、それぐらいの差があるということであろう。一品につき20Bぐらいずつね。となると、この三店で比較すると、いつもパパが自慢するように「『サクラ』は安い」のであろうか。
*
『北門』は焼き肉屋だから特別である。なんのかんのいっても一番日本で食べる焼き肉の味に近くて美味い店だ。先日、雨の日に出掛けたら『北門』が混んでいた。せっかく焼き肉を食べようとチェンマイランド通りまで来たのだからと、近くの『東京ヤキニク』という店に入ってみた。これが大外れ。店員に「社長は日本人か」と、色々質問してみたのだが、純粋なタイ人経営で日本人は一切噛んでいないらしい。だったら「東京」の名は止めて欲しいと、日本人として思う。名前にだまされた。いわゆる「日本風焼き肉屋」をタイ人がイメージで経営したもので、店内に演歌を流したりして日本人の客を意識しているが、日本風の焼き肉という本質をまったく解っていない。ひどいものだった。演歌もすり切れたような『北国の春』で聞きたくないものばかりだった。つまりここは、「日本風焼き肉というものを食ってみたいと願うタイ人が来る店」なのであろう。こんなところに来た日本人の私が悪い。
ここでも私はいつものようカルビ、タンシオから始まるワンパターン注文をした。値段は『北門』と同じで750Bぐらいだったが、とにかく肉が美味くない。大失敗。『東京ヤキニク』はダメ。二度と行かない。
(餘談ながら、韓国には「焼き肉の本場」というイメージがあるが、プルコギに代表される韓国焼き肉は、日本風焼き肉とはまったく別物である。私は日本風の方が好きだ。同じ意見の韓国人も多く、最近のソウルには、日本風焼き肉の韓国焼き肉の店も増えてきた。)
『赤門』だけ値段に幅があるのは冷酒のせいである。300ml入りの日本製冷酒が350Bで置いてあるのだ。これがけっこういける。
『赤門』では熱燗、冷やともお銚子一本100Bで飲める。でもこれは日本から船に揺られてきた箱の酒だと思う。添加物の臭いがきつくて私にはとても飲む気になれない。所詮一ヶ月程度の滞在だし日本酒が恋しくなるなんて事はない。どうしても飲みたけりゃスーパーマーケットの『TOPS』で、箱の酒よりはましな一升瓶を売っている。「松竹梅」が一升瓶で1600Bぐらいだったか。齢を取ってくると人間は量より質になる。このごろ日本酒にすっかりうるさくなってしまい、いくら異国とはいえ、日本酒ならなんでもいいとはならない。不味い酒しかないのなら飲まない方がいい。
それでも『赤門』に行き、イカの刺身を頼んだりすると「一本だけ飲んでみるか」と思ってしまう。初めてこの冷酒を見たとき、値段も見ずに日本と同じつもりでぐいぐいやってしまったから、会計金額にすこしばかり驚いた。レシートを持ってきた顔なじみのウェイトレス(着物を着て外股でバタバタと歩く。可愛いんだけどねえ、あの歩き方は×)が、ちょっと申し訳なさそうに「レイシュ、タカイネ」と言ったものだった。たいした金額ではない。日本の居酒屋と同じ程度の料金なのだが、どうしてもチェンマイ値段で考えてしまうから、飲食費で二千バーツを超すと、なんだかとんでもないことをしてしまったような気分になるのだ。
*
日本食レストランで一番高いのはロイヤルプリンセスホテルの中にある『みゆき』だろう。あそこに行って私が日本と同じ感覚で注文したら、三千バーツから五千バーツはすぐに行ってしまう。日本から来たお金持ちにご馳走になったことがあるので、味も値段の感覚も解っている。しかし日本食に飢えているわけでもないのにそれで散財をする気にはなれず、行っていない。店内に日本からの短期旅行者が何人もいて、日本と同じ味だと感心していたが、せっかくの短いタイ旅行なのに、なにも日本食を食べることもあるまいと思ったものだった。
そうだ、忘れないうちに最も大切なことを書いておこう。
それは、私は日本食など全然恋しくない、必要としていないということだ。タイ料理だけで一ヶ月ぐらいなんてことなく乗り切れる。街中から何キロか離れたアパートに住んでいるので、仕事が乗っているときは、朝の八時に近所の食堂でカオマンカイとバーミーナムの朝食(35B)を取り、午後まで仕事をする。その間の飲み物は、最近中国茶が気に入っている。カップに茶葉をそのまま入れて飲む方式のあれだ。午後一時ぐらいに一キロほど離れたタイ系中国人経営の飲茶屋に行き、点心とビアシンで昼飯(190B)を取る。部屋に帰って音楽を聴きつつ読書。一風呂浴びてまた仕事。夜九時に、アパートの隣の食堂で、トムヤムプラー、ソムタム、ガイヤーン、カオニオ、ビアシンで夕食(220B)、十時半就寝というような一日を送ったりすることも多い。街中に一度も出ていないし、日本人とも会っていない。私にとってチェンマイでの日本食はたいした意味を持っていないのだ。しかしこうして考えてみると、タイ料理三食分の値段が、日本食では一食分だという事に気づく。やはり庶民的食堂ではあれ日本食は高いのだ。
ではなぜ上記の日本食堂に行くのかという理由だが、それは親しくしていただいている方々への挨拶を兼ねているからである。『サクラ』ならパパ、『ゆみ』なら各務さん、『フジ』なら井上さん、『北門』なら神谷さんである。仕事が一息ついて、今夜は誰にも会わず、ひとりで日本酒でも飲みたいなあと思ったとき行くのが『赤門』になる。
もしも上記の店がすべてタイ人経営になり、経営者が親しい日本人でなくなったら、私は行かなくなるだろう。『サクラ』もパパがいないので最近はあまり行く気がしない。でもそのパパが、「シーちゃんを応援してやってよ」というから行っているようなものだ。
悪口はあまり書きたくないが。
『サクラ』の近くに「KAZU寿司」というのがある。
もうすぐ開店するという頃、シーちゃんが怯えていた。シーちゃんは「スシ」というのが日本人の大好きな食べ物だと知っていた。二人で話していたら、どうしてあんな店がわたしの引っ越してきたばかりの『サクラ』の近くにできるんだろう、わたしはついてないと、本気で悩んでいた。
私はそんなの関係ないよ、『サクラ』とは料理が違うから心配ないよとシーちゃんを慰めつつ、もしもチェンマイで美味い寿司が安く食べられるようになるのなら、それはそれで大歓迎だとも思っていた。
開店した。行ってみた。亭主は短髪のちょいと鯔背な日本人男性だった。もしかしてこの人は日本の寿司屋で修行して来た人かも知れない、チェンマイで本物の寿司が食えるかもしれないと期待が膨らんだ。とんでもない話だった。ひどかった。ひどすぎた。それは寿司ではなかった。場末の回転寿司屋で誰にも手を出されず一週間ぐらい回転していたような、ひからびた、寿司らしきものだった。今までの人生の中であんな不味い寿司ノヨウナモノは食ったことがない。
友人と三人でいた。ちょうどそのとき店の外を、シーちゃんが歩いて通り過ぎた。私はシーちゃんに手を振った。(だいじょうぶだよシーちゃん。ここは最悪だ)との気持ちを込めて。シーちゃんは自分の怯えるライバル店で私がいい気持ちで酔っていると思ったのか、プイと横を向いてしらんふりをした。それが今年の春のことである。すぐに潰れると思ったのに夏もまだ営業していた。誰が行ってるんだ、あんな店。不思議でならん。みのもんたでも救いようがないぞ。ボロボロのシャリに紙のように薄いネタが乗っている。そのネタが既にひからびている。あんなのは寿司ではない。私はあの亭主に、あんたに食の美学はあるのかと問いたい。
その他にもひどい日本食堂はいくつもあり、すべて体験済みだからいくらでも批判は出来るのだが、不味い店の不味い味について書いても、こちらも楽しくないのでやめることにする。上記、名前が登場している店は美味い店なのだ。尚、『宇宙堂』も美味い。評価対象に値する。でもここ一年以上、私流の「あれこれ注文長っ尻」をしていないので、失礼のないよう触れないことにした。
私のように普段は日本で暮らしていて、その感覚のまま外国に行き行動する者を普通人とし、若いときから世界中を旅してきたような人を旅行人と、假に分けることにしよう。その二種類の人間の違いが如実に現れるのは、金銭感覚と食作法のように私には思われる。 『赤門』で偶然Mさんと会ったことがあった。ひとりで食事をしていた私が新聞雑誌のコーナーに歩いていったら、やはりひとりで食事をしていたMさんと目が合ったのだ。何年ぶりかだった。やあやあ久しぶりとMさんが食べかけのうどんを手に、私の席に移ってくる。Mさんは私のテーブルの満艦飾を見て絶句した。そこにはテーブル狭しといくつもの料理が並び、日本酒とビールが両方とも注がれてあったからだ。四人用テーブルなのにMさんのうどんを置く場所がなかった。Mさんからすると私はやけくそでひとり宴会でもやっていたように見えたらしい。でもそれは『赤門』での私のいつもの食事風景だった。
Mさんは旅行人気質の人である。世界中を旅した後、チェンマイに落ち着いた。大金持ちである。五千万とも一億とも噂される金を日本から持ってきて、こちらの女性と結婚し、しあわせに暮らしている。子供もできた。でもMさんは私のような食事を今までしたことは一度もないと言った。Mさんにとって食事とは、単品を食べることだった。それからどこかに飲みに行く。その後、お腹が空いたらまたどこかで単品を食べる。
旅行人と普通人の違いは、日本における社交生活の差だろう。学生の時にふらっと出た海外に魅せられてとか、旅行人はもうそこから一気に行ってしまっているから、ごく普通の仲間内での居酒屋での宴会や飲み会、その手のものに疎い。いや、それ以前の持って生まれた体質なのかも知れない。学生時代でもサラリーマン時代でも、そういうみんなで盛り上がる宴会などよりも、異国の果てをザックを担いで歩いている方が楽しいというタイプだったのだろう。
普通人は違う。四人で集まるとする。仕事のお疲れさまでもいい、次の仕事の打ち合わせでもいい、集まること自体が一番の目的だったりする。居酒屋に行く。最初は「とりあえずビールね」である。そうして各自が三品、四品のつまみを注文する。ビールが来て乾杯する。次々とつまみが届く。テーブルの上は料理の置き場もないほどになる。他の人が頼んだものでも美味そうなものがあれば箸を出す。評価の高かったものはもう一人前、いや二人前追加だ。日本酒に行くか、焼酎をボトルで取れ、おれはウイスキーがいい、これが私達普通人の日常における酒の飲み方であり、私なんか毎日のようにこればかりである。この感覚のままチェンマイに行く。そうしてひとりぼっちではあるけれど、いつものよう三品、四品を頼んでビールを飲むということをする。それが前記の飲食費になるわけだ。
しかし旅先の場というのは、旅行人の場である。旅行人の常識が支配している。
『サクラ』の常連も、基本的にはみな旅行人だ。旅行人の飯の基本というのは、カレーでもいい、うどんでもいい、野菜炒めライスでもいい、とにかくしっかりと単品の飯を食うことであるらしい。そうして腹をくちくしてから、ジュースなりビールの小瓶なりを頼んで長話をする。会話を楽しむ。だから私のようにあれこれとつまみを取ってビール瓶並べて騒ぎまくっているオヤジは異色になってしまう。でもなあ、日本ではおれのやりかたの方が主流だぞ、ぜったい。
この感覚の差を、旅行人贔屓の視点で解釈すると、普通人には緊張感が足りないとなるのだろう。旅先では何が起きるか解らない。いつ飯が食えなくなるか解らない。だから食えるときに出来るだけ早く確実に満腹にするのだと。酒を飲んだり友人と話したりするのは、そのことが確保されてからの第二義的なものだと。それからでも出来ると。だらだらと酒と飯を同時進行させているのは、世界中が日本と同じように平和だと勘違いしている認識のなさから来ているのだ、と。
その通りかもしれない。そうかもしれないけど、チェンマイの日本食堂には、酒と飯を同時進行させても大丈夫なぐらいの平和は保証されているだろうし、普通人側から反論すれば、旅行人の飯の食い方は、単にびんぼ臭いだけなのである。
ここでまたシンプルな結論が言える。「食い物にうるさいヤツは、世界一周貧乏旅行なんか出来ない」ということだ。旅行人が食い物にうるさくない人たちであることもまた否定できない真実であろう。
私の飲食の仕方にショックを受けたらしいMさんは、来週もう一回ここ(『赤門』)で会いたいんだけどと言い、翌週私達は再会した。「この前みたいにやってみてよ」とMさんが言う。私は日本の居酒屋にいるつもりで、いつものようあれこれと注文した。Mさんも真似して刺身や海雲(もずく)酢を注文している。ビールと日本酒を一気に複数本頼む。テーブルに並んだいくつもの料理に好き勝手に箸を出しながら、Mさんは「こういうのっていいね。楽しいんだね」と言った。酒と飯の同時進行である。根っからの旅行人であるMさんが、新橋の居酒屋サラリーマン感覚を初体験した瞬間だった。
先日『ゆみ』でいつものような飲食をしていたら、ヒゲを生やした無口な日本人が入ってきた。彼はビアシンの小瓶とおにぎり三つを頼んだ。マンガを読みながら、黙々と握り飯を食い、ビールで流し込み、出て行った。その間、一言も口を利かなかった。こんにちはもなければごちそうさまもない。いろんな人がいる。ああいう日本社会じゃ通用しないような人もこの町は受け入れてくれる。だからああして日々節約し、メーサイで何度もビザ延長し、一日でも長くチェンマイにいようとするのだろう。だけどあれで夕食なら、チェンマイにいても山登りしていても差がないんじゃないかと思った。美味い空気と美しい夕焼けがある分、山の方がいいんじゃないかと。大きなお世話だけど。
*
私と同じく日本の居酒屋感覚で飯を食う日本人もチェンマイにはいっぱい来ている。カラオケにいるとよく彼らに会う。彼らがもしも『サクラ』や『ゆみ』に来たなら、私と同じような飲食をして、私がごく普通の日本人であることが証明されるのだが、残念ながら彼らがやって来ることはない。連休を利用した三泊四日ぐらいで来ている彼らには、そんなことをしている時間はないからだ。彼らの頭の中には「三泊四日の内に五人はやりたい」というようなことしかない。『サクラ』で酒飲んで盛り上がるなんて無駄な時間は使えないのである。だって日本では毎日そんなことをやっているのだ。なにもチェンマイまで来て日本の延長をしなくてもいい。なにしろ彼らはカラオケの店でカラオケをしないほど忙しい。ドドドッと四人ぐらいでやってきて、タイ人ガイドの説明を聞きつつ、女を指名する。五分後に女の着替えがすむやいなや肩を抱いてホテル直行である。お忙しいことだ。気持ち悪い日本語を話すタイ人ガイドは、これだけでもうバックマージンがすごいのだろう、文字通り〃笑いが止まらない〃とばかり、うひゃらうひゃらと笑っている。
十年前、『サクラ』で知り合った先輩方に誘ってもらい、イタリア料理屋、ドイツ料理屋、イサーン料理専門店など色々と教えてもらった。先輩はありがたい。その点に関しては心から感謝しているが、食事作法に関してはあまり楽しい思い出はない。
明日の夜、インド料理に行かないかと誘われる。うれしい。翌日を楽しみに待つ。『サクラ』で待ち合わせる。飯を食いに行くのに飯屋で待ち合わせるというのもすごいのだが、事情を知っているパパは、「楽しんでらっしゃい」なんて笑顔で送り出してくれる。いい時代だった。
いそいそと出掛ける。店で彼らは、なんとかカレーとナン(インドのパンですね)、水と注文する。ビールとカレーは合わないからこの水注文は正しい。きちんと一食百バーツ以内で納めるよう計算してあるらしい。私のようにアレも取りましょう、コレも取りましょう、このビール珍しいですね飲んでみましょう、インドの酒はないんですか、などとはやらないのだった。三人で行った。私は最初から今回は店を教えてもらうのだからと、私が払うつもりでいた。だからいつものよう自分のペースで飲食した。食事の後、私が払いますと言うより先に、レシートを見たひとりが「えーと、全部で600バーツだからひとり200バーツか」と言った。するともう一人が、おれはビールをほとんど飲んでいないのだからそれはおかしいと口をとがらせた。慌てて私が、きょうはぼくが払いますからと言う。するとその言いかたが彼を傷つけたらしく(?)、彼は自分の分は自分で払うと言って計算し、75バーツを叩きつけるように置くと、憤然として出て行ったのである。
気まずい雰囲気だけが残った。インド料理が悪いのではない。彼らと私の流儀の違いだった。
そんな私にも、なんの違和も感じず、チェンマイのあちこちで楽しく飲食出来る友人が何人かいる。チェンマイ在住ではない。彼らはみな日本からやって来る。そのひとり、タイ人女性と付き合っているDさんは、連休を利用してこまめにチェンマイに通ってくる現役サラリーマンである。サラリーマンであるということで私と飲み食いの感覚が共通している上に、ステディな恋人がいるということで女に飢えていないという点がプラス項目だ。一緒に遊ぶ条件が揃っている。彼と彼女と三人で、私にガールフレンドがいるときは四人で、私達は美味そうな店を見つけては食事に行く。上述のインド料理屋にも一緒に行った。あれこれ頼んで盛り上がり、こんな変な味の酒は飲めない、こりゃ辛くて食えないと大騒ぎすれば、インド人のおばちゃんも笑っていた。最高に楽しい夕食だった。飯は食い方次第で、楽しくもなり辛気くさくもなる。
『赤門』もよく一緒に行く。そこで彼がやることは私と全く同じだ。いくつもの料理を頼み、ビールを頼み、たまにはワインを飲んでみようとか、彼女たちに日本酒を飲ませてみようかなどと盛り上がる。日本の日常感覚の延長である。そんなとき私は、チェンマイでは異色でも、日本の社会では私の飲み方こそが王道なのだと自信を持つ。
そう思う一方でまた、こういう異国の地は旅行人の場であり、自分は本来日本にいるべき普通人なのだとも確認している。旅先で寂しいなどと思ったことは一度もないが、こんな時、自分は本来すべきではないことを無理にしている線路を外れた車輪のようなものなのだと感じたりする。本来の線路にもどるべきか、このまま野を転がり続けて行くのか、決断の時季に来ているようだ。


|