

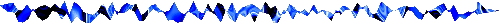


日本領事館が引っ越した。古いところしか知らない。毎回世話になっているレンタルバイク屋のスターに訊くと、ピン側の近くだろうという。それは以前の場所だ。そこから引っ越したのだ。有山パパのアパートに本を借りに行ったついでに、領事館の場所を教えてもらう。空港の近くの「チェンマイ・ビジネスセンター」の中に入ったという。それだけで理解できた。何度か見かけている。おれの住処の近くの、いかにも真新しいそれらしい建物だ。パパはチェンマイで作った十年物のパスポートを持っていた。見せてくれる。日本で作るものと違っているのは写真処理の方法だ。こちらで作るものは、一世代前のパスポートと同じように、写真を貼りラップを被せた作りである。日本で作る最新型と比べたらそりゃあ不細工な出来だけれど、贅沢は言っていられない。
翌朝。領事館に行く。九時前に着いた。アパートからバイクで十分もかからなかった。業務開始は九時だがもう十数人のタイ人が並んでいる。日本人はおれだけだ。
九時になった。仕事が始まる。受けつけ窓口は二つある。奥に位置した窓口の中には、銀縁の眼鏡を掛けた無表情な顔のタイ人男性がガラス越しに応対していた。絵に描いたような「底意地の悪そうな」というか「酷薄そうな」というか「爬虫類系の顔をした」というか、肉の薄い面立ちの変質者系の顔の男である。おれの方を冷たい視線でチラっと見た。ゾっとする。よくぞここまで嫌な顔つきのタイ人を見つけてきたものだ。未だかっておれはこんな冷たい顔つきのタイ人は見たことがない。こんなのを探すのはたいへんだったろうね、日本領事館。ごくろうさん。これだけであんたらの心構えが解るよ。人柄なんか関係なく選んだんだろうな。もしもあんたらが今までに苦労というものをしたことがあって、人の情に助けてもらった経験があるのなら、ぜったいにこんな顔の男は雇わないと思うよ。
奴の前に書類を手にしたタイ人が並んでいる。彼らはビザの申請だ。おじさんがいる。おばさんがいる。若い娘もいる。現在、タイ人の娘が日本へのビザを取得することは至難である。彼女はきょうビザを受け取りに来ていた。何の問題もなく受け取っている。ああ、話を聞いてみたい。彼女はどんな仕事をしているのだ。どんな状況でビザを申請したのだ。日本に何しに行くのだ。このタイ人が日本に行くのが困難な時代に、なぜそんなに簡単にビザが取得できるのだ。訊いてみたい聴いてみたいインタビューしたい。取材心が疼く。しかし今のおれにそんな時間的餘裕はない。去って行く彼女の背を未練げに見送る。
どうやら日本人がパスポートの申請をするのは、手前にある、いま誰もいない方の窓口であるらしい。
その窓口に行く。用のある人はチャイムを押せと書いてある。押してみる。ピンポーンと鳴った。何の反応もない。奥から人の出てくる気配もない。もう一回押す。ピンポーン。やはり何の反応もない。続けて押す。ピンポーンピンポーン。まったく何も変わらない。押しっぱなしにする。ピンポーンピンポーンピンポーンピンポーン。誰も出てこない窓口でチャイムを押し続けるおれを、タイ人が不思議そうな顔で見ている。チャイムが鳴り続ける。爬虫類男が、噛みつきそうな顔でおれを睨みつけた。しらんふりをしておれはチャイムを押し続ける。おれは日本人だ。パスポートを一日も早く作らねばならない状況にいる。ここは日本領事館だ。用のある人間はチャイムを押せと日本語で書いてある。だからおれはチャイムを押す。だいたいが日本領事館なのに日本人がひとりもいないというのはどういうことなのだ。外務省の左遷コースであるチェンマイ領事館に派遣された役人は、ひたすら一日も早い帰国を待ち焦がれるという。そうなんだろうな。そういう役人が仕切っている役所だからこんなにいい加減なのだろう。
もう開館時間を三十分も過ぎている。もしも係員がいないのなら爬虫類男が一言おれに説明すればいい。三十分待てでもいい、午後から来いでもいい。なんらかのサジェスチョンがあればおれはそれに従う。でも奴はおれを睨むだけで口は利かない。おれに出来るのはただチャイムを押し続けることだけだ。
弁明しておくが、おれはこんなことが好きなタイプではない。世の中にはこういう闘い(?)が好きで好きでたまらないという人がいる。『サクラ』で知り合った人に、一見おとなしそうなのだが、実はとんでないファイター(?)で、権力と闘うのが生き甲斐だという人がいる。彼は成田で渡される黄色い紙(伝染病の自己申告用紙ですね)のすべての項目にチェックを入れて渡す。それで通り過ぎる。当然係員が慌てて追いかけてくる。その係員と悶着を起こすのを彼は楽しみにしているのだ。「あんたはどんな権利があって私にこの紙を渡すのか、私はこの紙に記入しなければならない義務があるのか、これは国民に対する強制なのか、あんたはいったい何様なんだ!」と始まるのである。向こうが何かを言うと、うまくその揚げ足を取り、また攻め込む。時には胸ぐらを掴んだりする。あちらが暴力を振るえないことを計算尽くなのだ。なんという悪趣味だろう。しかし彼にとっては、これこそが不当な国家権力と闘うということであり、喜びの瞬間なのである。わからん。わかりたくもない。そもそもあの黄色の紙をチェックする係官は〃国家権力〃なのか? 下っ端の空港職員に見えるが。
でも日本では知り合うはずのないこういう珍しい人と出会えるのもチェンマイの魅力のひとつである。『サクラ』で知り合った人はバラエティに富んでいて楽しい。あまりに異様な彼の性格に興味を持ち、日本でも何回か会っていたが最近はちょっと距離をおいている。いつもはおとなしいのに何かのきっかけでいきなり豹変する人というのは、やはりちょっと怖い。
おれは彼とは違う。一切ゴタゴタとは関わり合いたくないと、自分の世界だけを大事にする事なかれ主義者だ。それがなぜかこの時は珍しくむきになり、普段の自分からは信じられないようなエキセントリックな行動を取っていた。おれなりに追いつめられていたのだろう。
チャイムを押し続けるおれ。鳴り続けるチャイム。ざわめくタイ人。険しい目でおれを睨む爬虫類男。なのに奥からは誰も出てこない。いったいこの日本領事館というのはどうなっているのだろう。勤務しているのはこの爬虫類男ひとりだけなのか。
何分ぐらい経ったろう。色の黒いのっぺりとした顔の女性が奥から現れた。涼しい顔で着席すると「お待たせしました」と日本語で言い、何事もなかったかのように、「パスポートの申請ですか」と問うた。上手な日本語だ。カンボジア人みたいな顔をしている。おれの考える典型的クメイル人の顔である。何人なのだろう。そりゃあタイの日本領事館に勤めているのだからタイ人なのだろうが、どこの地域だ。どう考えても北部ではない。イサーンか。南部かも知れない。
彼女のあまりに何気ない態度に、おれの怒りは行き場を失ない萎んでしまっていた。いったいどうなるのだろうと見守っていたタイ人達はほっとし、爬虫類男は険しい顔のままいつもの仕事にもどる。見事だった。彼女はまるでチャイムが一回鳴っただけで出てきたかのように振る舞っていた。肝が据わっている。おれは一枚上手の彼女を認めざるを得なかった。するとこのまますんなり申請が通るのではと希望的に思えてくる。しかし世の中、そううまくはいかない。
写真に定規を当てたりしてチェックしていた彼女は、「写真の顔が小さすぎますね」と言った。春に来たとき、チェンマイの写真屋でパスポート用と言って撮った写真だ。
「この写真では受けつけるわけにはいきません」
写真の撮り直しである。参った。この忙しいときに。

 街中の写真屋まで走る。一方通行を行ったり来たりしつつ走るから五キロぐらいはある。自分のバイクがあって天気がいいから苦にはならないが、領事館のあるのは街外れだ。ソンテオやトゥクトゥクで来た人なら、この二度手間は腹が立つことだろう。 街中の写真屋まで走る。一方通行を行ったり来たりしつつ走るから五キロぐらいはある。自分のバイクがあって天気がいいから苦にはならないが、領事館のあるのは街外れだ。ソンテオやトゥクトゥクで来た人なら、この二度手間は腹が立つことだろう。
春に撮った時と同じ顔なじみの写真屋に行き、このパスポート用の写真、顔が小さくてダメだと言われたぞと文句を言う。一言ぐらい謝るかと思ったら、中国系タイ人の亭主は「へえ、ああそう。なんでかなあ」と他人事のように言った。ぜんぜん気にしていない。すこしは気にしろよ。「それよっかさ、ちょっとこれ、なんて書いてあるか訳してくれない」と言うと、サンカンペーン出身の美人の女房に奥から日本のラジコン雑誌を持ってこさせる。なんなんだこいつらのこのこだわりのなさは。すこしはこだわれよ。自分の仕事だろう。体から力が抜ける。怒る気にもなれない。
写真を撮る。パスポート用の写真だ。いつもボサボサ頭のおれもさすがに鏡を見て髪を梳かした。なにしろこれから十年間、世界中を一緒に歩く写真である。「今度は大丈夫なんだろうな、今度またダメだと言われたらいくらおれでも怒るからな」と出来上がった写真を見ながら言う。すこしは悪いと思っているのか、亭主も写真を何度も見て、顔の大きさが規定のサイズになっているか確認している。いつの間にかおれは、たぶん大丈夫だろう、もしダメならもう一度来ればいいや、なんて思っている。この国に来ると何もかもがどうでもよくなってくる。元々の性根からして投げやりなおれは、ここにいると溶けかかったアイスクリームのようにだらしなくなる一方だ。そういう性格だからおれは、この国での毎日の充実感に人一倍こだわる。生活にメリハリをつけ、日々の緊張を無理矢理作り出す。それを失くしたら、この国の熱気に当てられ命にさえ投げやりになりそうで……。
日本のラジコン雑誌の記事を頼まれて訳す。模型好きの亭主は広告のラジコンの船が欲しくてしょうがないらしい。エンジンなしの飾り物で5800バーツ。エンジンを積んでラジコンで水の上を走らせるなら(フルキット)12800バーツだと、日本円をバーツに換算しつつ説明してやる。彼らが雑誌のアルファベットを読み、船の名前だと思ってたびたび口にする言葉は模型会社の名前だった。それを指摘し、カタカナで書かれている船名をタイ文字で書いてやる。が英語の出来る連中だからアルファベットでいいのだった。意味のない親切だ。こういうクラスの連中はおれがタイ文字を書くと、感心するのではなく鼻で笑ったりする。「12800バーツなら安いね。すぐ注文しよう」と夫婦の意見は一致したようだ。小さな店だが商人というのはどこの国でも(見かけよりも)裕福なんだなと思う。
領事館にもどり、写真を替え再び申請。無事受理される。カンボジア人みたいな顔のお姉さんに、五年物か十年物かと問われる。値段はあまり変わらないから十年物を申請した方が得だ。特におれは日本のパスポートが紺色になってしまったことが気に入らず、「日本人のパスポートは赤だ。なんで紺色になんかしたんだ。赤だ、赤にもどせ!」とあちこちで力説していた。それは赤いパスポートを見ただけで、人畜無害の日本人と安心されノーチェックで通してもらうということを諸外国で何度も経験してきたからだった。ナショナルカラーというものは必要だ。金払いがよく、集団になるとうるさいものの、基本的にはおとなしくて扱いやすい日本人のカラーとして、赤いパスポートのイメージは世界に浸透していた。おれの年齢だと東京オリンピックのあの赤のブレザーの印象だ。なにも敢えてそれを変える必要はあるまい。パスポートに五年物と十年物ができて、十年物にまたあの赤色が復活したと知ったとき、おれは快哉を叫んだ。嫌いな紺色のパスポートを愛しい赤色に変えたくてしょうがなかった。この五年の間に、早く赤の十年物パスポートに切り替えたいと何度口にしたことだろう。(ずっと以前の日本のパスポートが赤でなかったことや、偽造を防ぐために定期的に色を変えていることは承知の上で書いています。)
なのにやっと切り替えるときが来たというのに、こんな事情で出来の悪いタイ製パスポートを作ることとなり、しかも撮り直してきた写真には、いかにも昨夜遅くまで深酒をしていましたという醜くむくんだ中年男の顔が写っていたのだった。信じられない。タイ人のカメラマンは下手だ。この写真は人間の内面の美しさというものをまったく無視している。写し出していない。これではまるでおれが酒でむくんだ顔をした頭の禿げかかった醜い五十男みたいじゃないか。失礼な。おれは腹立ち、目の前の鏡を見る。写真と同じ顔の男がいた。そのままじゃん。
じっと考える。それはほんの数秒だったかも知れない。おれは必死に頭を回転させ、醜い写真と出来の悪いタイ製赤のパスポートを十年持つよりも、ここはとりあえずあと五年間紺色で我慢して、五年後に日本で、紗を掛け何カ所か修正した美男の写真を貼った最新型赤いパスポートを手にすることにしようと決めたのだった。赤いパスポートに対する憧れを、むくんだ顔が力尽くで押さえ込んだようなものだった。五年物を申請する。発行費用の支払いは出来上がりの時でいいという。

 中三日で出来あがると知る。日本の一週間よりもずっと早い。これなら昆明行きも楽勝だと喜んだおれは、すぐにまた予定外の事態にがっかりさせられることになる。どうも今回はぬか喜びが多い。 中三日で出来あがると知る。日本の一週間よりもずっと早い。これなら昆明行きも楽勝だと喜んだおれは、すぐにまた予定外の事態にがっかりさせられることになる。どうも今回はぬか喜びが多い。
申請したのが七月二十三日の木曜日だった。
七月二十七日、火曜日の朝に出来上がるという。そうなれば、火曜日の朝に中国領事館でビザを申請し、水曜日の午後に受け取り、七月二十九日、木曜日の午後の昆明行きに間に合う。
チェンマイ・昆明は木曜と日曜の週二便だ。二十九日の木曜日に乗れなかったら八月一日の日曜日まで飛行機はなく、そうなると昆明に一足先に着いたカメラマンに迷惑を掛けることになる。よかった。なんとかなりそうだ。
ところがそのタイ人女性館員が急に気づいたように言う。そういえば二十七日、二十八日はタイの祝日でした。ですからこの二日をスキップして、出来上がりは二十九日、木曜日になりますと。
目の前が真っ暗になる。なんちゅうこっちゃ。前から祝日は決まっていたろうが。急にいま祝日が出現したわけでもないだろう。なんでもっと早く言わん。木曜日の朝に出来上がって、それからビザを取り、午後二時二十五分発の飛行機に乗ることは、どう考えても不可能だ。ビザの発行には最短でも丸一日かかるのだ。ここまできてまたどんでん返しである。
もうしょうがない。おれは潔く諦めた。いやこういうのは潔くとは言わないな。いやいやながら仕方なく諦めざるを得ない状況に追い込まれやけくそで諦めるのに、潔くなんて形容をしちゃいかん。もうなんでもいいや。とにかく諦めた。諦めざるを得ない。日本に電話して、カメラマンの彼にはホテルで二泊ほど待っていてもらうことにしよう。世界中のあちこちを一緒に動いた仲だ。解ってくれるだろう。そうそう、メーリムのチェンマイ・リゾートも彼と一緒に来たんだった。あれですっかりタイが好きになった彼は、その半年後の新婚旅行も迷うことなくプーケットを選んだものだった。謝ろう。彼に謝って許してもらおう。編集部にも頭を下げよう。もういい。おれはもう諦めた。

おれはいつもチケットを購入しているP&Pトラベルに出向いた。七月二十九日の昆明行きチケットを八月一日に替えてもらうためだ。するとプラーニットといういつも世話になっているインド人のお姉さんが耳寄りな情報を教えてくれた。それが前述した「その日発行のビザ」である。なにしろ先週、プラーニットのところでチケットを買い昆明に行った客が、その方法で出発日の前日に取得したというのだから間違いない。更には、当日発行というビザがあることは、彼女が自分のオフィスから中国領事館に電話をして、そういう緊急処置があることを発見したというのだから確実な情報だ。やってくれるね中国領事館。いかにも中国らしい処置だ。そりゃなあ、ビザなんて簡単な作業で作れるものなんだから、高い金を払えばその日の内に作ってやるという姿勢は正しい。日本領事館もあと千バーツ上乗せするから二十七日にパスポートを発行できないか? 出来ないんだよな。こういうことに関しては日本の役所は杓子定規で融通が利かないのだ。
プラーニットは、二十九日の朝にパスポートを受け取り、中国領事館でその日発行のビザを申請し、午後一番、二時に受け取って空港に行けば間に合うのではないかと言った。それと、八月一日の昆明行きは満席でキャンセル待ちしかないと。調べてみるとキャンセル待ちが十六人もいた。「花の博覧会」で昆明は今、世界中からの観光客で賑わっている。このキャンセル待ちはきつい。
うーむ。思わずおれは唸る。可能といえば可能かも知れないし不可能といえば限りなく不可能のような気もする。中国領事館の午後の部が開館してすぐ、二時にパスポートを受け取り、クルマをびんびん飛ばして空港に向かっても、二時十分にはなる。出発まであと十五分だ。いくらいい加減なタイでも、一応国際便であるチェンマイ・昆明便に、離陸時間十五分前のチェック・インは可能なのだろうか。
ここまで追いつめられれば度胸も据わる。おれはそれでやってみようと思った。いつも諦めが早かった。ボロボロになるまでの努力はしない。しがみつかない。執着しない。そういうふうに生きてきた。それでも旅をするようになって、いくらかねばり強くなったようではある。

成田十一時半発のビーマン・バングラディシュ航空に乗るのに、品川のアパートで目覚めたのが九時だというときがあった。友達が悪い。そいつらはおれが明日の朝早く出発すると知って、今夜は壮行会だ、徹夜で飲もうと仕掛けてきたのだ。ウイスキーだった。おれはストレートでしか飲まない。ピヨピヨだ。さすがに効いた。部屋に三時過ぎに帰ったことは覚えている。目覚ましを掛ける餘裕すらなかった。服を着たままぶっ倒れて眠った。朝の光で目が覚める。しまったと思う。もう九時だった。割れそうな頭を抱え、部屋で十分ほど悩んだろうか。行くべきか行かざるべきか。
品川から成田までタクシー代二万五千円をかけて今から行ったとして、最高に早く着いても十一時半だ。間に合わない。下手したらもう飛行機は空の上だ。それまでのおれなら諦めていた。ビーマンの安いチケットを捨てればいいことだ。「おまえらに潰されてひどい目に遭ったよ。チケット代、弁償しろよな」と冗談にすればすむ。それがおれのやりかただった。そうして生きてきた。べつに急いでタイに行く用事もない。来週出発でもいい。
なのにおれは十分後、中原街道にタクシーを捕まえに出ていた。意図を察知した運転手は頑張ってくれた。チンコンチンコンと警告チャイムが終始鳴りっぱなしだった。おれは車内で(無理だよなあ、タクシー代がもったいないよ。なんでこんなみっともないことしてるんだろ。帰りは荷物を抱え電車で成田からもどってくるのか。人には言えないなあ。うひゃあみっともねえ)と悲観的なことばかりを考えていた。なにしろ今までこんなかなりの確率で負けると解っている勝負をしたことがなかった。おれにとってこれはとんでもない賭けだった。
成田に着いたのは十一時半だった。正規の離陸の時間だ。タクシーを飛び降りてビーマンのカウンターに駆け込む。タクシー代を払ってここまで来た。来た以上は乗りたかった。乗れますかとの問いに、係の女性は「出発が遅れてますからまだだいじょうぶですよ」と微笑んだ。それだけでおれは、偉大なことを成し遂げたような気分だった。トラブル慣れしている人から見たらこんなのは苦労の内に入らないのだろうが、おれにとってこれは、今までの人生の中でも最も理不尽な行為に属する。
そのことで度胸がついたり、しぶとくなったとかの効果は全くない。それ以来おれは早め早めに空港へ出かけるようにはなった。出発前夜は深酒をしなくなった。それがまあ一番の収穫か。
今回も、さっさと諦めた方がいい。でも可能性があるなら、二十九日出発にかけてみたい。二十九日にパスポートを受け取り、中国領事館に向かい、その日発行のビザを申し込む。それを午後一番で受け取って空港に向かう。二時にすぐもらえるように、中国領事館には一度二十八日に出かけて事情を説明しておいた方がいいだろう。そうしよう。ダメかもしれないが、出来るだけのことをやってみよう。そう決めた。


チェンマイで出会った多くの先輩方からいくつもの旅行代理店を教えてもらった。みな自分だけのお気に入りチケット屋をもっていて、まるで身内の自慢話のようにその店のことを話す。といってそれが良い店とは限らない。あるベテラン旅行者が「あそこの店はタイ航空と特約しているからチケット発行も早いしサーヴィスも最高だよ」と推薦してくれた店は、おれにはやたらと気位の高い愛想の悪い店でしかなかった。あるチェンマイ在住者が「ボクなんかもう十年もあそこばっかりだよ。ボクの名前を言えば値引きしてくれるから」とわざわざ電話を掛けて紹介してくれた店は、タイにありがちな、入店したこちらをまったく見えませんとでもいうように無視するとんでもない店だった。
おれはたとえどんなに美味い店だろうと、寿司屋のオヤジに怒鳴られながら寿司を食う気はないように、いらっしゃいませも言えないようなチケット屋には、いかにそこが破格の安い店であろうと行かない。そしてまた客を怒鳴りつけるような寿司屋に本当に美味い店などないように、接客の基本も出来ていないような店で、飛び抜けてチケットが安いという店もなかった。
あれこれと学んだ今だから言えることだが、諸先輩方のこの「愛しのチケット屋」を分析すると、これは極めて日本人的な情の世界であることに気づく。つまり、一度親切にしてもらった、便宜を図ってもらったという過去の恩を、日本人は忘れないのである。大事にするのだ。チケット屋からするとそれは、恩義を感じて貰うほどのものでもないのだが、まだ初心者でそれほど状況が読めていなかった諸先輩方は、実際以上に感謝してしまったりする。そうして通う。親しくなる。益々愛着を持つようになる。「あの店はいいよ。親切だし安いし」と大絶賛したりする。だがその店の世話になっていないおれのようなのが、客観的かつ冷静に観察すると、それはたいして魅力のない並の店でしかなかった。蓼食う虫も好きずきというレヴェルだった。ほんとにもう、今だからこんな分析もできるのだが。
チェンマイの旅行代理店でチケットを買おうとして一番苛立つのは、例えば、ヴェテランの店員がこちらの話を聞いてチケットの手配をしているときに、おなじみさんが来るとそちらに行ってしまい、もどってこなくなったりするようなことである。時には代理として新人の店員をこちらに差し向けたりする。それまででほぼ済んでいた話をもう一度最初からしなければならない。新人の店員には決定権がなく、やたらと上司に相談に行くので、なかなか話が進展しなかったりする。そんなところにやっとヴェテラン店員がもどって来て、これで話がまとまるかと思ったら、そこにまた別のおなじみさんがやってきて、となったりする。几帳面で生真面目な日本人としては苛立つことこの上ない。胃に悪い。「おなじみさん」として認知されるとプラス項目がいくつかあるらしいが、そうでない場合は不愉快になることばかりなのである。
日本でおなじみさんになるのは簡単だ。HISに代表される旅行代理店の一支店で、同じ人から三回もチケットを買えば、すぐになれる。パソコンにデータも入るし、行く先を告げるだけで手配をしてくれるツーカーの仲になれたりする。だが基本的に愛想が悪く仕事熱心でないタイ人に、親しんでもらう客になるのはたいへんなことだ。
チケット屋で何回も航空券を買うと、確実に愛想が良くなり、いついってもニッコリと微笑み、いつ来たの、いつまでいるの、次はいつ来るのと話しかけてくるタイ人が出来るようになる。恰幅のいい店のオーナーだ。オーナーにとって毎回航空券を買ってくれるこちらは上客である。顔も覚える。名前も覚える。愛想も良くなる。気分がいい。一番偉いオーナーに百年の知己のように扱われ、VIP気分でカウンターに座るとき、この慇懃さは平店員にも通じるものと思う。当然だ。だがその後の現実は厳しい。現実にチケットを扱う店員にとっては、月に百枚売ろうが一枚しか売れなかろうが、給料は同じなのである。彼らにとってこちらは、自分たちには何のメリットももたらさない異国人でしかない。自分たちに益をもたらさないのだから、彼彼女らに笑顔が見えることはない。もしも年に三回、三年以上、海外への航空券を同じチケット屋で買ったなら、日本だとちょいとしたおなじみさんだと自負できるだろう。だがタイでは、たとえ百回以上買おうとそれは平店員にとって何の意味も持たない。
端的な話、チェンマイのチケット屋でおなじみさんとして、入店するなり店員から笑顔で迎えられ、優先的に扱ってもらいたかったら、チケットを千万円買うよりも、これぞと思った店員をさりげなく誘い、彼らと、きっと同伴するであろう彼らの友人に、タイスキでも奢ってやった方がずっと効率的だ。あなたはそこで、確実に彼らに益をもたらした人間となる。次回来るときに、お土産として資生堂の化粧品でも買ってきてやれば完璧になる。笑顔を見せたら損をするとでも思っているのではないかというぐらい普段は無愛想な店員も、あなたが店に行くたびに笑顔で迎えてくれるようになるだろう。ただし、一度奢ったなら、毎回来るたび、五回も十回も百回でも奢ってくれるものと向こうは思いこむ。一回土産を買って行けば毎回買ってきてくれるものと期待されるのだ。
旧『サクラ』の近くに「クイーン・ビー」という旅行代理店がある。ここでその底なし沼にはまった日本人は多い。お人好しの日本人は、飯を奢りちょいとした土産物を買ってきてやるだけで、女子店員が笑顔で迎えてくれるようになることが嬉しくてたまらないのだ。かくいうおれも被害者のひとりなのでこの心理はよく解る。異国の、しかも北の外れの町に初めて来た時、知り合いはいない。知り合いが出来ても、それは水商売の女という金絡みだ。そんなとき、旅行代理店の社員という素人女性(!)に、笑顔で迎えて貰う仲になることは、なにかの勘違いを誘発してしまうのである。これはこれでひとつの経験でもある。麻疹を一度経験しておくことも悪くはない。


タイ人の気質というのは、子供っぽいというかその場しのぎというか三歩歩いたら過去を忘れるニワトリというか、日本人から視ると不思議でならない面がある。
彼らが何かの仕事をやっていたとする。假におれの提出した何かの書類を作っていたとしよう。役所、警察、銀行、旅行会社、どこでもいい。彼はおれのための書類を今作っている。そこに同僚が話しかける。「ねえ、この書類の件なんだけど」と。すると彼は「どれどれ」とその書類を覗き、「ああ、これはね」と、同僚に教えるまではいいが、やがてそれに熱中してしまうのだ。おれの書類はほったらかしにされてしまうのである。延々とこちらの目の前でその書類をああでもないこうでもないと検討したりする。その書類と共にいなくなってしまうこともある。そこにまた誰かが違う件に関して話しかけたりすると、彼は性懲りもなくそちらにまた興味を持ってしまうから、もはやおれの書類は二世代前の興味となってしまい、彼がもどって処理してくれることはしばらくの間期待できない状態になってしまうのである。何度これに泣かされたことだろう。
日本人なら優先順位というものを忘れない。受けつけた順番というものを。そういう発想がタイ人にはないようだ。いつでも自分が一番興味を持っているものに対して素直に、感情の赴くままに行動する。子供の時からそうだし、大人になって仕事をするようになってもそれは変わらない。だからあんなに自然に浮気できるのだろうし、こだわりもなく離婚するのだろうし、いつでも楽天的に生きていられるのだろう。
ここで視点を替えると、順番が守られないなら、遅く行ったのに早く処理してもらうという、順番を飛び越すこともやりようによっては可能だということに気づく。
実はおれも一度だけ、この恩恵に属したことがある。もう何年前になるか忘れたが、『宇宙堂』で借りたバイクを盗まれたことがあった。今年の春、チェンマイ在住の服部氏と話をしているとき、なぜかその話題になり、「へえー、『宇宙堂』で借りたバイクを盗まれて弁償させられたバカがいると聞いたことがありましたけど、そうですか、あれはあなただったんですか」と驚かれた。わるかったなバカで。それはともかく、このバイク盗難事件は女も絡んだおもしろい話なので、また改めてワンテーマとして書くことにしよう。名つけて「宇宙堂バイク盗難事件」だ。
その盗まれたバイクの盗難届を出しに、チェンマイ警察署に行ったときのことだった。ナベちゃんとナンシーが一緒だ。おれ達の前には何人もの先客がいた。順番からいうと五、六番目だったろう。みんなは廊下の長椅子で順番を待ち、その先にある個室の中では、警官と向き合ったタイ人が、調書のようなものを作ってもらっていた。しかしナンシーは廊下で待たず部屋に入っていった。待っている人たち、調書を作っている状況を無視して警官の前に行き、一気に話を始めたのだ。いきなり話しかけられて警官は驚く。タイ人も顔を上げた。おとなしそうな中年男だった。警官とタイ人の表情に関係なく、ナンシーは一方的にこちらがバイクを盗まれたことを説明する。まくし立てる。おれは、警官が「今はこの人の番だ。あちらで待っていなさい」と言うだろうと思った。おとなしそうなタイ人も、さすがに今はおれの番だと主張すると思った。
信じられないことが起こった。最初はそれまでの調書を作り続けていた警官だったが、次第にふんふんとナンシーの話に頷き始め、興味をそそられたのか、それまで制作中だったタイ人の調書を押しのけ、新しい調書にナンシーや『宇宙堂』の名を記入して、おれ達の調書を作り始めたのである。なんちゅういい加減さだ。追いやられたタイ人は、喧嘩に負けた犬のようにすごすごと廊下へ出ていった。怒れよ、おい。おれは割り込んだ自分のことも忘れて、いい加減なタイ人の警官とおとなしいタイ人に腹を立てていた。今までこんな順番を無視する奴らの散々被害者になってきたが、まさかここで加害者の気分を体験するとは思わなかった。それは決して気分のいいものではなかった。
おれ達は来たばかりなのに、先客五、六人を飛び越していきなり自分の番にしてしまったのだ。ナンシーは平然としている。ナベちゃんが苦笑しつつ、「すごいよ、ナンシーは」と言った。そう言うナベちゃんの目には恥じらいがあった。たしかにおれはそれを感じた。ナベちゃんも日本人だった。「まったく」とだけおれも相槌を打った。忙しい時間に盗難届というしち面倒なことを素早く片づけてもらいおれ達は助かっていた。ナンシーに感謝しなければならない。でも日本人であるおれとナベちゃんには、順番というマナーを無視した行動に、気恥ずかしい想いもつきまとっていた。それはとても新鮮で衝撃的な経験ではあったけれど。

 あちこちの店に出入りしている内、誰に教えてもらったわけでもないのに、いつしかおれはP&Pという旅行代理店に通うようになっていた。P&Pトラベルはターペーロードにある。ターペー門に向かって五十メートルぐらい手前の左側になる。ここ何年か世話になっている旅行代理店だ。 あちこちの店に出入りしている内、誰に教えてもらったわけでもないのに、いつしかおれはP&Pという旅行代理店に通うようになっていた。P&Pトラベルはターペーロードにある。ターペー門に向かって五十メートルぐらい手前の左側になる。ここ何年か世話になっている旅行代理店だ。
経営者は、頭にターバンを巻いたシーク教徒のインド人である。その奥さんが「踊るマハラジャ」のミーナみたいな顔をしたプラーニットになる。二人とも爺さんの出はインドのデリーだが、完全なタイ系インド人なので夫婦間でもタイ語で話している。いうまでもなく英語も問題ない。
いい店である。おれがこの店に落ち着いたのは、プラーニットの仕事ぶりに惚れたからだった。彼女は仕事が出来る。有能だ。なんといっても経営者としてこの店を仕切っているから、決定権も決断力もある。拠って仕事が早い。前述したような、客との商談中に中座するような失礼なこともしない。
もしかしたらこのページを読んでP&Pトラベルを利用したいと思う方がいるかもしれないので、この店に関する注意事項をひとつだけ書いておこう。いや、べつに改めて書くほどのものでもないか。いやいや意外に重要なことかも知れないのでやはり書いておこう。
それは、ここにはこの夫婦以外に五、六人のタイ人女性が働いているのだが、その彼女たちが全員、泣きたくなるほど無能だということである。だからこの店を気持ちよく利用したいなら、一切彼女たちと関わってはならない。それが唯一の注意事項になる。
タイのデパートなどで、客を無視してペタペタと化粧直しをしている店員、カウンターの内側にうずくまって飯を食っている店員、いらっしゃいませもありがとうございますも言わない店員、声を掛けるとこちらをジロっと睨む店員などに出会うと、(ああ、タイだ。おれはタイに来たんだなあ)としみじみと嬉しく、ふつふつと怒りがこみ上げてくるものだが、ここの女達もそういうクソたわけたタイ人の性癖を完璧に備えているのである。なーんにもせず役にも立たない雁首だけ揃えて座り、うすらぼんやりと鼻くそをほじったりしている。
(タイでは人前で鼻くそをほじることが失礼にあたらないので、日本ではあまり目にすることの出来ない若い女の鼻くそほじりというものをたっぷりと鑑賞出来る。女の鼻くそほじりを見るのが大好きで、あれを見るともうたまりません、思わず前が膨らんでしまいますというような鼻くそほじりフェチには夢のような国といえる。ふんぐりもんぐりふんぐりもんぐりとひたすら鼻くそをほじる女を目の前で見ていると、マスメディアの横暴や北朝鮮に腹を立てていた自分が空しくなり川辺に行って石を投げたくなる。尚、この鼻くそほじりの習慣が人前で許されるのももちろん下層階級だけの話である。)
その何もしない無能女達の間を、「踊るマハラジャ」プラーニットが八面六臂の活躍で動きまくっている。その他大勢の彼女らがやるのはプラーニットが契約した書類のコピーや、かかってきた電話を彼女に繋いだり、その程度のことでしかない。
たぶん有能なタイ人というのは(プラーニットは見かけは完全なインド人だが気質の半分はタイ人といえる)、人に教えて育てるというよりも、可能な限りなんでも自分でやってしまうのだろう。仕事ぶりを観察していると、プラーニットが雇い人などに何も期待せず、なんでも自分で仕切ろうとしていることが解る。彼女らが無能だからひとりで取り仕切るのか、ひとりですべて取り仕切ってしまうからいつまで経っても彼女らが無能なのか。
言えるのは、こういう固定給をもらう立場のタイ人には、日本人的上昇志向のようなものは微塵もないということである。「なぜあなたはすべてを自分で取り仕切ってしまうのか。もっと私たちを信頼して欲しい。私達にも仕事を教えて欲しい。私達も仕事にやりがいが欲しい」などとは彼女らは間違っても思わない。所詮固定給なのだから、コピーや電話の取り次ぎのような楽な仕事であるほど楽しいと考える。たとえ経営者が彼女らに仕事を教えて育てたとしても、彼女たちには教えてくれた人や会社に対しての忠義心というものがないから、すこしでも給料の高い店があったら覚えた仕事を売り物にして移籍するだろう。それだと教えた分だけマイナスになる。そういえば、短大を出たばかりの若い娘二人を、自分の跡継ぎにと一から仕事を教え育てあげたら、すぐに二人だけで獨立され、怒り狂っていた旅行代理店の女社長を知っている。
『サクラ』のシーちゃんの場合でも、一番苦労していたのは、いかにして自分の仕事を雇い人達に分散して行くかだった。それはドゥアンやレックという長年勤続してくれるスタッフを手に入れることで可能になった。それでも朝の仕込みはシーちゃんの仕事だ。事情を知らない人が、最近のシーちゃんは裕福になって夕方にならないと店に顔を出さないなどと言ったりするが、朝の七時に『サクラ』に行けば、そういう感覚がいかに狭い視点からの解釈であるか気づくだろう。
P&Pトラベルに行くとき、おれは必ずプラーニットがいることを確認してから店に入るようにしている。今まで彼女がいないときに行って散々嫌な目に遭ってきたからだ。こういう店の女というのは、短大卒やビジネススクール卒のようなタイ人にしては半端な高学歴を誇っていて、平均的日本人のおれ達より自分たちの方がずっと格上だと思っていたりするから餘計に始末が悪い。こちらがもう何十回も女主人からチケットを買っているのを見ていて、タイ語が話せるのも知っているくせに、プラーニットのいないときに行くと紋切り型の下手な英語で話しかけてきたりする。それでいて既に金が払ってあり、その日受け取ることになっているチケットを渡してくれという簡単な用件を述べると、その件に関してはわたしの担当ではないので解らないなどとタイ語で弁明を始めたりするのである。なんの役にもたたん。だったら最初から話しかけてくるな。
というわけで、「踊るマハラジャ」プラーニットは、おれが今まで見た中でも一番速いブラインドタッチをこなす至極有能な女性である。ギター歴三十年のおれも指先の小器用さにはすこしばかり自信がある。ブラインドタッチはかなり速い。今ちょっと彼女を意識して最高の速さで打ってみた。駄目だ。とても敵わない。おれの場合はあくまでも「速く打っている」「打つのが速い」なのである。打つという行為が前面に出ている。彼女の場合はキイボードの上を指が滑っているように見える。打っているように見えない。テレビや映画の、本当は打てない役者がやたら素早く打つという嘘のシーンのように見えるかもしれない。正に名人芸である。(と持ち上げておきながら、いま反論を思いついた。彼女のようなプロというのは、打つ単語がかなり限定されているのではないだろうか。彼女の目にも留まらぬ速さでタイピングされるのは、航空会社の名であり、東京、バンコク、ロサンゼルスというような地名であり、日付であり、ファースト、ビジネス、エコノミーというクラス分けであり、予約状況を見るための接続パスワードであったりするだろう。それを十年以上毎日毎晩やっていたら、考える前に指が動くという絶妙のブラインド・タッチも、絶賛するほどのことでもないのではないか。もしも彼女に「子供時代の思い出」「初めて彼(亭主)と会ったとき」のような〃作文〃を書かせたなら、普段打ち慣れない単語を使うため、彼女のタッチはかなり遅くなるのではないか。むしろ頭に浮かんだことを、どんなことでも一定のスピードでブラインド・タッチ出来るおれの方が、総合的には速いと言えるのではないか。そんな負け惜しみを考えた。)
チェンマイからどこかの国に行き、またチェンマイにもどり、バンコクから日本に帰りたいなどというときには、彼女に相談するといい。彼女は素早くキイボードを叩き、エアラインと接続時間をプリントアウトして、たちまちの内にあなた好みのプランを作ってくれるだろう。
チケットの値段はもっと安い店があることと思う。バイクで目につく店を覗いて値段をメモして行けば、その時の最安値の店が見つかる。一バーツでも安いチケットを買いたいと金額にこだわる人はそういう店で買えばいい。おれがこの店を推奨するのは、有能な人間にテキパキと仕事をこなしてもらいたい、気分良くさっさと購入したい。そのためには百や二百の金はどうでもいいという人に対してだけである。
店を覗き、彼女がいるかどうか確認してから入ってください。繰り返しますが、彼女以外のスタッフは無能です。「踊るマハラジャ」を知っている人ならプラーニットを見間違えることはないでしょう。そっくりの美人です。太ってますけど。


 二十七日、二十八日の連休は、佛教関係の祝日らしく酒が飲めなかった。法律である。飲むと警察に捕まるのだ。夕方『ゆみ』に行くとユパちゃんが、これなら飲めるよと日本製の焼酎を指さした。焼酎だと色が透明だから、飲んでいる時に警官が来ても、水だとごまかせるのだという。んなアホなという感じだが、その辺は以心伝心で、警官も見逃してくれるということなのだろう。焼酎の梅干し入りを頼む。めったに飲まないお湯割り焼酎で顔が熱くなった。 二十七日、二十八日の連休は、佛教関係の祝日らしく酒が飲めなかった。法律である。飲むと警察に捕まるのだ。夕方『ゆみ』に行くとユパちゃんが、これなら飲めるよと日本製の焼酎を指さした。焼酎だと色が透明だから、飲んでいる時に警官が来ても、水だとごまかせるのだという。んなアホなという感じだが、その辺は以心伝心で、警官も見逃してくれるということなのだろう。焼酎の梅干し入りを頼む。めったに飲まないお湯割り焼酎で顔が熱くなった。
その後、ロータリーのEさんさんの店に向かった。全店閉店していた。皆勤賞のパパは今夜どうしているのだろう。オープンスペースでビールを飲んで楽しむところだから、酒が出せないのでは商売にならないのだ。今年の夏から出来たこの屋台村を、おれは最初「メイピンの近くの屋台村」のように不確かな呼び方をしていた。いつしか誰かが「ロータリー」と呼び始め、それが通称となったが、それでもまだおれはその呼び方を信じなかった。一部日本人だけの通称なのだと思っていた。だっておれなんかの考える英語のロータリーと通じ合う部分がないからだ。ところがその夜、入り口にある普段は見ることもない看板を見上げてみたら、タイ文字ででっかく「ラーン・ロータリー」と書いてあった。「ロータリーの店」である。ここは正式にロータリーでよかったのである。
ロータリーは全店閉店していたが、その後ゴーゴーバー『スポットライト』に行くと、入り口の電気を消して神妙を装ってはいるものの、店内ではみんな飲みまくって大騒ぎしていた。もちろん経営者が警察にたっぷりと鼻薬を嗅がせてあるから可能なのだ。
酒を飲んではいけない祝日というのは、一応の決まり事で、いわば建前である。きちんとした店は休業していた。中レヴェルのレストランは開いていても酒は出さない。一方ではまたここのように、神妙なふりをしながら中ではドンチャン騒ぎをやっている店もある。この辺のタイのいい加減さは大好きだ。
そういえばもう忘れかけていたが、七、八年前、『サクラ』で、昼間、湯飲み茶碗でビールを飲んだことがあった。あれも酒を飲んでは行けない祝日だった。この日だろう。酒を飲んではいけない祝日は年に何日かあるのだろうが、夏だったし、時期的にもきっとこの日だ。懐かしい。なつかしいなあ。おれにとっての『サクラ』と『宇宙堂』とは、以前の二店並んでいた時代のことになる。パパがいてナベちゃんがいたあの時代だ。二店が別れてしまったとき、おれの中で『サクラ』も『宇宙堂』も終った。だからおれのこの日記は、これから過去へと遡って行く。おれが語りたいのは、古き良きあの『サクラ』と『宇宙堂』なのだ。
パパを囲んだ丸テーブルで、もしも警官が通りかかっても見咎められないようにとビール瓶は奥の厨房に置き、茶碗にビールを注いでは、お茶を飲むふりをしながら飲んだのだった。誰がいたっけ。神谷さん、ナベちゃん、浦野さん、笹井さん、金子さんか。岩崎さんはいたか? イサオちゃんはあの頃から夕方にならないと顔を出さなかった。酒に卑しい話だが、警官が来たらとぼけなくちゃ、あまり赦い顔になるのはまずいななどと意識しつつ、そうして飲むビールというのもそれはそれで美味かった。そしてその楽しみは、日本人のお客さんにサーヴィスでお茶を出してやりたいと思うパパが、日本製の茶碗をいくつも用意していたからこそ出来たことでもあった。あの頃おれは、日本で仕事に疲れると『サクラ』に行きたくてたまらなくなったものだった。
卑しいと言えば、パソコンに字がないので表示出来ないが、中国語でビールは、口編に卑しいという文字を書き、それに酒である。ピージューと発音する。口に卑しい酒だ。おれのように毎日欠かさず水代わりにビールを飲む者には実感として伝わる当て字である(ビール、ビアのビに漢字を当てたのだ)。初めて訪中したとき、ビアといってもビールと言っても通じず、これはもう久しぶりにとんでもない国に来てしまったなと頭を抱え、会話本を見ながらピージューと言ってやっと通じた時の嬉しさをつい昨日のことのように思い出す。そうだ、その中国に行くために、なんとしてもパスポートとビザをクリアしなければならないのだった。
さあて、いよいよ勝負の二十九日である。

 
|